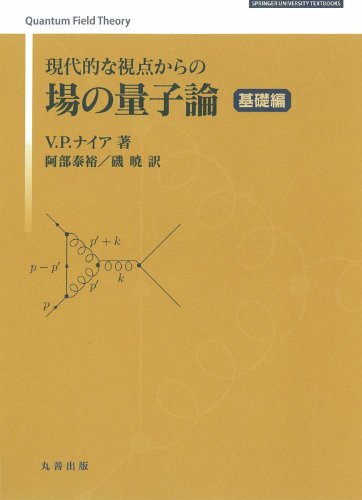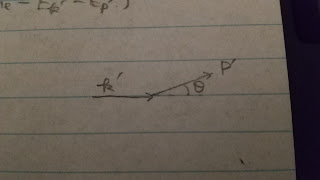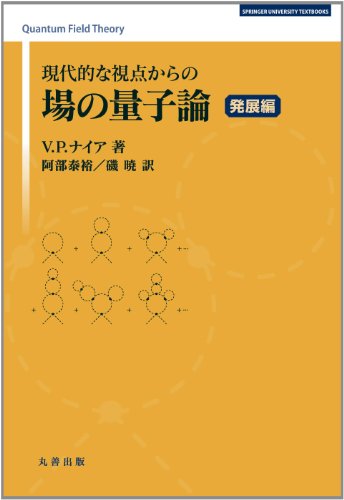\[ \begin{eqnarray} \L &=& \L_0 + \L_g + \L_q + \L_\Phi + \L_{yuk} \\ &=& -\qu ( F_{\mu\nu}^{a} )^2 -\qu ( G_{\mu\nu} )^2 - \bar{q}_L \ga_\mu \left( \d_\mu - ig b_\mu^a t^a - i \frac{g^\prime}{6} C_\mu \right) q_L \\ && - \bar{u}_R \ga_\mu \left( \d_\mu - i \frac{2}{3}g^\prime C_\mu \right) u_R - \bar{d}_R \ga_\mu \left( \d_\mu + i \frac{1}{3}g^\prime C_\mu \right) d_R \\ && - \bar{l}_L \ga_\mu \left( \d_\mu - ig b_\mu^a t^a + i \hf g^\prime C_\mu \right) l_L - \bar{e}_R \ga_\mu \left( \d_\mu + ig^\prime C_\mu \right) e_R \\ && - ( D_\mu \Phi )^\dagger (D_\mu \Phi ) - \la \left( \Phi^\dagger \Phi - \frac{v^2}{2} \right)^2 \\ && + \left[ f_{(e)} \bar{l}_L \Phi e_R + f_{(u)} \bar{q}_L \widetilde{\Phi} u_R + f_{(d)} \bar{q}_L \Phi d_R + h.c. \right] \end{eqnarray} \tag{1} \]
となることを見てきたが、このモデルの真空(基底)状態のエネルギーを極小化することを考えたい。$\la > 0$, $v^2 > 0$ のとき、真空状態は期待値$\bra \Phi^\dagger \Phi \ket = \frac{v^2}{2}$となり、対称性の破れを意味する。つまり、
\[ \bra \Phi \ket = \bra 0 | \Phi | 0 \ket = \binom{0}{v/\sqrt{2} } \]
が要請される。では、残りの対称性はどうなるだろうか?
$U(1)_Y$: $\Phi^\prime = e^{i \al} \Phi $, $\Phi = \binom{\phi^+}{\phi_0}$より$\phi_0^\prime = e^{i \al} \phi_0$ なので $U(1)_Y$は破れる。
$SU(2)_L$: $\Phi^\prime = g \Phi$なので、3成分はすべて破れる。
$U(1)_{em}$: $Q= \left( I_3 + \frac{Y}{2} \right)$, $\phi_0^\prime = e^{-i \frac{\al}{2} + i \hf \al} \phi_0 = \phi_0$なので$U(1)_{em}$は保存される。これが
前回note03で$Y(\Phi ) = +1$とした理由である。
真空からの場の揺らぎを考えよう。これらは摂動論の枠内における粒子に対応する。ヒッグス・スカラー場を次のようにパラメータ表示する。
\[ \Phi (x) = U^{-1} (\zeta ) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et (x) }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \]
\[ U (\zeta ) = \exp \left[ i \frac{\zeta^a (x) t^a }{v} \right] \]
元々の複素スカラー場$\phi^+ (x)$と$\phi_0 (x)$が4つの実スカラー場$\zeta_i (x)$と$\eta (x)$でパラメータ表示されている($i = 1,2,3$)。これらの揺らぎ場の真空期待値(VEV)はゼロとなる。
\[ \bra \zeta_i \ket = \bra \eta \ket = 0 ~~ \longrightarrow ~~ \bra \Phi \ket = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \]
これらを式(1)に代入する。$\bra b_\mu \ket = \bra C_\mu \ket = 0$であり、フェルミ粒子にも同様の関係が成り立つので、これらの揺らぎ場は場そのものと同様に扱える。
\[ \L_\Phi = - \left[ D_\mu \left( U^{-1} (\zeta ) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right) \right]^\dagger \left[ D_\mu \left( U^{-1} (\zeta ) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right) \right] - \la \left[ \begin{pmatrix} 0 & \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} -\frac{v^2}{2} \right]^2 \]
ここで、ゲージ場とフェルミ場を次のように再定義する。
\[ \begin{eqnarray} U \d_\mu U^{-1} - ig U b_\mu^a t^a U^{-1} &=& - i g b_{\mu}^{\prime a} t^a \\ - i g^\prime C_\mu &=& -i g^\prime C_{\mu}^{\prime} \\ U l_L &=& l_L^\prime \\ U q_L &=& q_L^\prime \\ e_R &=& e_R^\prime \\ u_R &=& u_R^\prime \\ d_R &=& d_R^\prime \end{eqnarray} \]
プライムのついた新しい場は元の場とゲージ変換によって関係づけられており、新しい変数を使うことはあるゲージ固定を行うことと等価である。ここで選択されるゲージは「ユニタリーゲージ」と呼ばれる。このユニタリーゲージを使うとラグランジアン(1)は次のように変形できる。
\[ \begin{eqnarray} \L &=& -\qu ( F_{\mu\nu}^{a} )^2 -\qu ( G_{\mu\nu} )^2 - \bar{q}_L \ga \cdot \left( \d - ig b \cdot t - i \frac{g^\prime}{6} C \right) q_L \\ && - \bar{u}_R \ga \cdot \left( \d - i \frac{2}{3}g^\prime C \right) u_R - \bar{d}_R \ga \cdot \left( \d + i \frac{1}{3} g^\prime C \right) d_R \\ && - \bar{l}_L \ga \cdot \left( \d - i g b \cdot t + i \hf g^\prime C \right) l_L - \bar{e}_R \ga \cdot \left( \d + ig^\prime C \right) e_R \\ && - \left[ D_\mu \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right]^\dagger \left[ D_\mu \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \right] - \la \left( \frac{(v + \et )^2 }{2} - \frac{v^2}{2} \right)^2 \\ && + \left[ f_{(e)} \bar{l}_L \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} e_R + f_{(u)} \bar{q}_L \begin{pmatrix} \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \\ 0\end{pmatrix} u_R + f_{(d)} \bar{q}_L \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} d_R + h.c. \right] \end{eqnarray} \tag{2} \]
ヒッグス・ラグランジアンの変形
\[ - ig b_\mu^a t^a - i \frac{g^\prime}{2} C_\mu = \begin{pmatrix} -ig \frac{b_\mu^3}{2} - i \frac{g^\prime}{2} C_\mu & - ig \frac{b_\mu^1 - i b_\mu^2 }{2} \\ - ig \frac{b_\mu^1 + i b_\mu^2 }{2} & ig \frac{b_\mu^3}{2} - i \frac{g^\prime}{2} C_\mu \end{pmatrix} \]
なので
\[ \frac{b_\mu^1 \pm i b_\mu^2 }{2} = W_{\mu}^{\mp} \]
と定義すると
\[ D_\mu \Phi = \left( \d_\mu - ig b_\mu^a t^a - i \frac{g^\prime}{2} C_\mu \right) \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i \frac{g}{\sqrt{2}}W_\mu^+ \frac{v + \et}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \d_\mu \et + \frac{i}{2} ( g b_\mu^3 - g^\prime C_\mu ) \frac{v + \et}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \]
\[ \begin{eqnarray} ( D_\mu \Phi )^\dagger ( D_\mu \Phi ) &=& \frac{g^2}{4} W_\mu^+ W_\mu^- (v + \et )^2 + \hf ( \d_\mu \et )^2 + \frac{( g b_\mu^3 - g^\prime C_\mu )^2 }{4} \frac{(v + \et )^2}{2} \\ &=& \frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W_\mu^- + \frac{g^2 v}{2} W_\mu^+ W_\mu^- \et + \frac{g^2 }{4} W_\mu^+ W_\mu^- \et^2 + \hf ( \d_\mu \et )^2 \\ && + \frac{v^2}{8} \begin{pmatrix} b_\mu^3 & C_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g^2 & -g g^\prime \\ -g g^\prime & g^{\prime 2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_\mu^3 \\ C_\mu \end{pmatrix} + \frac{v}{4} ( g b_\mu^3 - g^\prime C_\mu )^2 \et \\ && + \frac{1}{8} ( g b_\mu^3 - g^\prime C_\mu )^2 \et^2 \tag{3}\end{eqnarray} \]
質量行列を対角化
\[\begin{eqnarray} \hf M_Z^2 Z_\mu Z_\mu &=& \frac{v^2}{8} \begin{pmatrix} b_\mu^3 & C_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g^2 & -g g^\prime \\ -g g^\prime & g^{\prime 2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_\mu^3 \\ C_\mu \end{pmatrix} \\ &=& \hf \begin{pmatrix} Z_\mu & A_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} M_Z^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_\mu^3 \\ A_\mu \end{pmatrix} \end{eqnarray} \]
ここで質量行列の対角化には次の直交変換を用いた。
\[\begin{eqnarray} Z_\mu &=& \cos \th_W b_\mu^3 - \sin \th_W C_\mu = \frac{g b_\mu^3 - g^\prime C_\mu}{\sqrt{g^2 + g^{\prime 2}}} \\ A_\mu &=& \sin \th_W b_\mu^3 + \cos \th_W C_\mu = \frac{g^\prime b_\mu^3 + g C_\mu}{\sqrt{g^2 + g^{\prime 2}}} \tag{4} \end{eqnarray}\]
\[ \tan \th_W = \frac{g^\prime}{g} ~~~~~ \mbox{$\th_W$: Weinberg angle} \]
\[ M_Z^2 = \frac{v^2}{4} ( g^2 + g^{\prime 2} ) ~~ \longrightarrow ~~ M_{Z^0} = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g^{\prime 2}} \]
式(3)の第1項は荷電ベクトルボソン$W^\pm$の質量項になる。
\[ \frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W_\mu^- = M_{W^\pm} W_\mu^+ W_\mu^- ~ , ~~~~~~ W_\mu^+ W_\mu^- = \hf (b_\mu^1 )^2 + \hf (b_\mu^2 )^2 \]
\[ ~~ \longrightarrow ~~~ M_{W^\pm} = \frac{gv }{2} \]
よって、式(3)は次のように表せる。
\[ \begin{eqnarray} ( D_\mu \Phi )^\dagger ( D_\mu \Phi ) &=& M_W^2 W_\mu^+ W_\mu^- + \hf M_Z^2 Z_\mu Z_\mu + \hf ( \d_\mu \et )^2 \\ && + 2 \frac{M_W^2}{v} W_\mu^+ W_\mu^- \et + \frac{M_W^2}{v^2} W_\mu^+ W_\mu^- \et^2 \\ && + \frac{M_Z^2}{v} Z_\mu Z_\mu \et + \frac{M_Z^2}{2 v^2} Z_\mu Z_\mu \et^2 \tag{5}\end{eqnarray} \]
さらに式(2)の項を考えていく。
\[\begin{eqnarray} \frac{\la}{4} \left[ (v + \et )^2 - v^2 \right]^2 &=& \frac{\la}{4} ( 2 v \et + \et^2 )^2 = \la v^2 \et^2 + \la v \et^3 + \frac{\la}{4} \et^4 \\ &=& \hf m_H^2 \et^2 + \frac{m_H^2}{2 v} \et^3 + \frac{m_H^2}{8 v^2} \et^4 \tag{6}\end{eqnarray}\]
ただし、\( m_H = \sqrt{2 \la v^2 } \)とした。また、
\[ \begin{eqnarray} f_{(e)} \bar{l}_L \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} e_R + h.c. &=& f_{(e)} \bar{e}_L \frac{v + \et }{\sqrt{2}} e_R + h.c. \\ &=& \frac{f_{(e)} v}{\sqrt{2}} \bar{e} e + \frac{f_{(e)} }{\sqrt{2}} \bar{e} e \et \end{eqnarray} \]
となる。ここで、$\bar{e}_L e_R + h.c. = \bar{e} e$, $e = e_L + e_R$を用いた。同様に、
\[ \begin{eqnarray} f_{(u)} \bar{q}_L \begin{pmatrix} \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \\ 0\end{pmatrix} u_R + h.c. &=& \frac{f_{(u)} v}{\sqrt{2}} \bar{u} u + \frac{f_{(u)} }{\sqrt{2}} \bar{u} u \et \\ f_{(d)} \bar{q}_L \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{v + \et }{\sqrt{2}} \end{pmatrix} d_R + h.c. &=& \frac{f_{(d)} v}{\sqrt{2}} \bar{d} d + \frac{f_{(d)} }{\sqrt{2}} \bar{d} d \et \end{eqnarray} \]
以上から、次のような質量スペクトルが得られる。
\[ \begin{eqnarray} && M_W = \frac{gv}{2}~, ~~ M_Z = \frac{v}{2} \sqrt{g^2 + g^{\prime 2}} = \frac{gv}{2}\frac{\sqrt{g^2 + g^{\prime 2}}}{g} = \frac{M_W}{\cos \th_W} \\ && m_H = \sqrt{2 \la} v ~,~~ m_e = \frac{f_{(e)}}{\sqrt{2}} v ~,~~ m_u = \frac{f_{(u)}}{\sqrt{2}} v ~,~~ m_d = \frac{f_{(d)}}{\sqrt{2}} v \tag{7}\end{eqnarray} \]