前回のエントリー「青空と夕焼けに想う(3)ナイアのエッセイから」の続きで、このシリーズの最終回です。このシリーズでは数式を表示するのに MathJax を駆使しましたが、以前のエントリーだけの知識では、記述が大変だったので慣れている省略記号を使えるようにMathJaxのマクロの設定をしました。参考にしたサイトは、
http://gilbert.ninja-web.net/math/mathjax1.html
http://www.yamamo10.jp/yamamoto/comp/WEB/MathJax/index.php
https://whyitsso.net/others/mathjax.html
です。MathJaxの公式ページも参考になりました。前回の第3章では数式は出てきませんでした。水の吸収スペクトルの図が2つ出てきましたね。昔、中学2年生の時、数学の授業中に『水とはなにか』という本を読んでいて先生に没収された記憶があります。内容が面白くてつい読み進めてしましました。いま調べてみると古い本ですが、新装版
が出ています。その日、担任の先生に職員室に呼び出されて注意されたのでそれ以降は真面目に授業受けていましたが、学校での数学や物理(あと語学)は習熟度別のクラスにする方がいいと思います!これらの教科の習得は水泳を習うようなものなので、スイミングスクールのように進度別にする方が効率がいいはずです。その方が先生・生徒の関係も良くなるはずです。いまの中学・高校のことはよく分かりませんが、もし差別化すると協調性がなくなったりいじめの温床になると危惧しているのであれば、そんなことは無いと思います。子供はクラスメイトの特長を先生や大人よりも敏感に感じ取っているし、特定の分野が苦手だからと言ってバカにするようなことをするのは(私の経験から言って)むしろ大人のほうです。協調性については他の授業や学校行事で充分教育できると思います。
話しがだいぶ逸れてしまいましたが、ナイアのエッセイの最終章はこれまでの議論の備考として少し専門的になりますが以下の2つのトッピックを紹介しています。
1.臨界状態の密度揺らぎ関数の臨界指数の導出についての最近の発展。特に、場の量子論の発展に関連した共形ブートストラップの手法から得られた結果が紹介されています。
2.レイリー散乱の特徴である$\om^4$-依存性とは異なる$\om$依存性をもつ散乱過程の紹介。光子との散乱媒体として具体的に、超伝導体の小球体と量子ホールの滴 (droplet) が考えられています。それぞれの散乱過程において、前者は$\om^0$-依存性、後者には$\om^2$-依存性があることが示されています。
場の量子論を使えば第一原理から散乱過程を解析できるので議論がスッキリしていていいですね。相互作用項が分かれば$S$-行列の演算子が決まり、そこから散乱振幅、微分散乱断面積、崩壊確率、寿命、全散乱断面積などの物理量が機械的に求まります。相対論的粒子、非相対論的粒子の散乱過程に興味がある方、勉強したい方はこちらの教科書
http://gilbert.ninja-web.net/math/mathjax1.html
http://www.yamamo10.jp/yamamoto/comp/WEB/MathJax/index.php
https://whyitsso.net/others/mathjax.html
です。MathJaxの公式ページも参考になりました。前回の第3章では数式は出てきませんでした。水の吸収スペクトルの図が2つ出てきましたね。昔、中学2年生の時、数学の授業中に『水とはなにか』という本を読んでいて先生に没収された記憶があります。内容が面白くてつい読み進めてしましました。いま調べてみると古い本ですが、新装版
が出ています。その日、担任の先生に職員室に呼び出されて注意されたのでそれ以降は真面目に授業受けていましたが、学校での数学や物理(あと語学)は習熟度別のクラスにする方がいいと思います!これらの教科の習得は水泳を習うようなものなので、スイミングスクールのように進度別にする方が効率がいいはずです。その方が先生・生徒の関係も良くなるはずです。いまの中学・高校のことはよく分かりませんが、もし差別化すると協調性がなくなったりいじめの温床になると危惧しているのであれば、そんなことは無いと思います。子供はクラスメイトの特長を先生や大人よりも敏感に感じ取っているし、特定の分野が苦手だからと言ってバカにするようなことをするのは(私の経験から言って)むしろ大人のほうです。協調性については他の授業や学校行事で充分教育できると思います。
話しがだいぶ逸れてしまいましたが、ナイアのエッセイの最終章はこれまでの議論の備考として少し専門的になりますが以下の2つのトッピックを紹介しています。
1.臨界状態の密度揺らぎ関数の臨界指数の導出についての最近の発展。特に、場の量子論の発展に関連した共形ブートストラップの手法から得られた結果が紹介されています。
2.レイリー散乱の特徴である$\om^4$-依存性とは異なる$\om$依存性をもつ散乱過程の紹介。光子との散乱媒体として具体的に、超伝導体の小球体と量子ホールの滴 (droplet) が考えられています。それぞれの散乱過程において、前者は$\om^0$-依存性、後者には$\om^2$-依存性があることが示されています。
場の量子論を使えば第一原理から散乱過程を解析できるので議論がスッキリしていていいですね。相互作用項が分かれば$S$-行列の演算子が決まり、そこから散乱振幅、微分散乱断面積、崩壊確率、寿命、全散乱断面積などの物理量が機械的に求まります。相対論的粒子、非相対論的粒子の散乱過程に興味がある方、勉強したい方はこちらの教科書
の第7章を参考にしてください。読んでいるうちにナイア流の記号の使い方、考え方に自然になれると思います。では、ナイアのエッセイ最終章の日本語訳(意訳)は以下の通りです。
4 備考
密度の相関関数による散乱過程の定式化を使って臨界タンパク光 (critical opalescence) の現象を説明することもできる。液体・気体の臨界点付近では、密度揺らぎが非常に大きくなるため散乱断面積が増加し、気液平衡状態で乳白光が現れる。この現象を解析する標準的な手法として物質の圧縮率のデータを使うものがあるが、より直接的に相関関数の振る舞いからこの現象を考察することもできる。臨界点では相関関数は
\[
\bra N (x) N(y) \ket = \frac{C}{ | x - y|^\eta } \, \sim \,
\int \frac{d^3 q }{(2 \pi )^3}
\frac{ e^{i\vec{q} \cdot ( \vec{x} - \vec{y} )} }{| \vec{q} |^{3 - \eta }}
\tag{35}
\]
という形に書ける。ただし、$C$は定数。臨界指数 $\eta$ は相関関数の振る舞いを特徴づける値である。密度相関関数のフーリエ変換については1章で構造因子として式(16)で見た。これと上式より、$| \vec{q} | = | \vec{k} - \vec{k}^\prime | \sim \om$ がゼロとなる低エネルギー散乱では相関関数が発散することがわかる。
水の場合、液相と気相の区別がなくなる臨界点はおよそ温度647K (374℃) 、圧力218気圧 (22MPa) である。臨界タンパク光をレイリー散乱と関連付けることは、100年以上も前のアインシュタインにまで遡る。しかし、臨界点での相関関数の理解はここ数十年の間に進めらててきたものであり、その中で最も目立った成果は、普遍性 (universality) の概念である。物理系の臨界現象はこの普遍性のクラスで分類される。つまり、系の詳細や様々な相互作用一つ一つが重要ではなく、それらの相互作用の重ね合わせ効果として現れるある種の普遍的な振る舞いが決定的となり、それにより臨界点における物理システムが分類されるという考え方である。水の臨界現象は3次元イジング模型と同じ普遍性クラスに分類される。したがって、臨界点での相関関数 $\la \bra N(x) N (y) \ket$ の性質は、スピン場(あるいは自己相互作用する3次元スカラー場)の相関関数を調べることで決定できる。これは、WilsonとFischerが繰り込み群と$\ep$-展開の枠組みを使って行った解析の典型的なケースである。彼らの結果によると最小オーダーの近似で臨界指数は $\eta = \hf + (1/108)$ で与えられる [1]。それ以来、数値的にも解析的にも数多くの異なる手法が試みられている。最近のものとして、共形ブートストラップの手法がある。この手法は、臨界点での理論に現れる演算子の満たす代数に基づいており、代数的なアプローチによる場の量子論の発展と関連している。この手法により臨界指数をより精度よく求めることができ、今の場合は $\et = 0.518151(6)$ となる [2]。この結果はとても驚くべきことで、ある意味愉快でもある。というのも、場の量子論に現れる演算子の代数のようなものから臨界タンパク光やレイリー散乱という現象の解析に直接的な影響を与えることができるというのだから。
これまでに導いた散乱の公式が例外的な状況にも応用できることを見るのもまた楽しいものである。例えば、超電導物質でできた小球体との散乱を考えてみよう。超伝導体内では伝播光子は質量をもち、低エネルギーあるいは長波長ではこの質量が支配的になる。この質量項を相互作用項として扱うと、散乱振幅は
\[
\A = i \mu^2 \int d^4 x ~ \ep \cdot \ep^\prime
\frac{e^{-i kx + i k^\prime x}}{\sqrt{2\om V 2 \om^\prime V}}
\tag{36}
\]
と書ける。ただし、$\mu$は超伝導体中を伝播する光子の有効質量を表す。第2章の式(30)の分子にあった $\om \om^\prime$ がここではないことに注意しよう。式(30)の $\om \om^\prime$ は、有効作用に現れる(ベクトル・ポテンシャル$A$ではなく)電磁場の強さテンソル$F$のためであった。また、頭に入れておくべきこととして、偏光テンソルは対応する波の伝播ベクトルと垂直に与えられる。それ以外の解析はこれまでの解析とほぼ同じであり、2章の式(32)に相当する微分断面積の公式
\[
d \si = \frac{\mu^4}{32 \pi^2} | F ( \vec{q} ) |^2
(1 + \cos^2 \th ) d \Om
\tag{37}
\]
が得られる。もしどこか地球以外の惑星の大気が超伝導物質の粒子の分布で構成されているとすれば、その惑星の住人はおそらく青い空と赤みがかった夕焼けを享受することはできないでしょう。
つぎに、さらに想像力を膨らませて、ディスクの重ね合わせを考えよう。ここで、各ディスクは量子状態にあり、量子ホール効果を表示しているものとする。2次元の量子ホールの滴(しずく、droplet)において、カレントの期待値は
\[
\bra J_i (x) \ket = \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \ep_{ijk} \hat{n}_k F_{0j} (x)
\tag{38}
\]
で与えられる。ただし、$\hat{n}_k$は滴表面にたいする単位法線ベクトル、$\nu$は充填率である。これより、
\[
\bra J_i (x) J_j (y) \ket = \frac{e^2 \nu}{2 \pi} e_{ijk} \hat{n}_k ~ \d_0
\del^{(4)} ( x -y)
\tag{39}
\]
となる。よって、散乱振幅は
\begin{eqnarray}
\A &=& i \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \int d^4 x \om^\prime
\frac{( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} }
{\sqrt{2 \om V 2 \om^\prime V}} \, e^{-i ( k - k^\prime ) x }
\\
&=& i \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \om^\prime
\frac{( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} }
{\sqrt{2 \om V 2 \om^\prime V}} F ( \vec{q} ) 2 \pi
\del ( \om - \om^\prime )
\tag{40}
\end{eqnarray}
となる。これより微分断面積
\[
d \si = \left( \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \right)^2 \frac{\om^2}{ 16 \pi^2 }
\, |F ( \vec{q} ) |^2 |( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} |^2
\tag{41}
\]
を得る。偏光について和をとり、平均化すると
\[
d \si = \left( \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \right)^2 \frac{\om^2}{ 32 \pi^2 }
\, |F ( \vec{q} ) |^2 \left[
\frac{( \vec{k} \cdot \hat{n} )^2 \om^2 +( \vec{k}^\prime \cdot \hat{n} )^2 \om^2 + [( \vec{k} \times \vec{k}^\prime ) \cdot \hat{n} ]^2}{\om^4}
\right]
\tag{42}
\]
となる。散乱断面積は振動数についてより緩やか、つまり$\om^2$の依存性を持つ。構造因子$F( \vec{q} )$はいつものように量子ホール滴の分布の情報から決まる。ディスクが$z$軸方向に重なりあっているとし $n$ 番目のディスクの $z$ 座標を $z_n$ とすると、量子ホール滴は$(x,y)$-平面に広がっているので、構造因子は
\[
F( \vec{q}) = \int_{\rm disk} d^2 x ~ e^{i q_1 x + i q_2 y} \sum_{n}
e^{i q_3 z_n}
\tag{43}
\]
と書ける。ディスクの幾何学的な変形の効果は、一般的な場合のこの$F(\vec{q})$を用いて簡単に評価できる。
\[
\bra N (x) N(y) \ket = \frac{C}{ | x - y|^\eta } \, \sim \,
\int \frac{d^3 q }{(2 \pi )^3}
\frac{ e^{i\vec{q} \cdot ( \vec{x} - \vec{y} )} }{| \vec{q} |^{3 - \eta }}
\tag{35}
\]
という形に書ける。ただし、$C$は定数。臨界指数 $\eta$ は相関関数の振る舞いを特徴づける値である。密度相関関数のフーリエ変換については1章で構造因子として式(16)で見た。これと上式より、$| \vec{q} | = | \vec{k} - \vec{k}^\prime | \sim \om$ がゼロとなる低エネルギー散乱では相関関数が発散することがわかる。
水の場合、液相と気相の区別がなくなる臨界点はおよそ温度647K (374℃) 、圧力218気圧 (22MPa) である。臨界タンパク光をレイリー散乱と関連付けることは、100年以上も前のアインシュタインにまで遡る。しかし、臨界点での相関関数の理解はここ数十年の間に進めらててきたものであり、その中で最も目立った成果は、普遍性 (universality) の概念である。物理系の臨界現象はこの普遍性のクラスで分類される。つまり、系の詳細や様々な相互作用一つ一つが重要ではなく、それらの相互作用の重ね合わせ効果として現れるある種の普遍的な振る舞いが決定的となり、それにより臨界点における物理システムが分類されるという考え方である。水の臨界現象は3次元イジング模型と同じ普遍性クラスに分類される。したがって、臨界点での相関関数 $\la \bra N(x) N (y) \ket$ の性質は、スピン場(あるいは自己相互作用する3次元スカラー場)の相関関数を調べることで決定できる。これは、WilsonとFischerが繰り込み群と$\ep$-展開の枠組みを使って行った解析の典型的なケースである。彼らの結果によると最小オーダーの近似で臨界指数は $\eta = \hf + (1/108)$ で与えられる [1]。それ以来、数値的にも解析的にも数多くの異なる手法が試みられている。最近のものとして、共形ブートストラップの手法がある。この手法は、臨界点での理論に現れる演算子の満たす代数に基づいており、代数的なアプローチによる場の量子論の発展と関連している。この手法により臨界指数をより精度よく求めることができ、今の場合は $\et = 0.518151(6)$ となる [2]。この結果はとても驚くべきことで、ある意味愉快でもある。というのも、場の量子論に現れる演算子の代数のようなものから臨界タンパク光やレイリー散乱という現象の解析に直接的な影響を与えることができるというのだから。
これまでに導いた散乱の公式が例外的な状況にも応用できることを見るのもまた楽しいものである。例えば、超電導物質でできた小球体との散乱を考えてみよう。超伝導体内では伝播光子は質量をもち、低エネルギーあるいは長波長ではこの質量が支配的になる。この質量項を相互作用項として扱うと、散乱振幅は
\[
\A = i \mu^2 \int d^4 x ~ \ep \cdot \ep^\prime
\frac{e^{-i kx + i k^\prime x}}{\sqrt{2\om V 2 \om^\prime V}}
\tag{36}
\]
と書ける。ただし、$\mu$は超伝導体中を伝播する光子の有効質量を表す。第2章の式(30)の分子にあった $\om \om^\prime$ がここではないことに注意しよう。式(30)の $\om \om^\prime$ は、有効作用に現れる(ベクトル・ポテンシャル$A$ではなく)電磁場の強さテンソル$F$のためであった。また、頭に入れておくべきこととして、偏光テンソルは対応する波の伝播ベクトルと垂直に与えられる。それ以外の解析はこれまでの解析とほぼ同じであり、2章の式(32)に相当する微分断面積の公式
\[
d \si = \frac{\mu^4}{32 \pi^2} | F ( \vec{q} ) |^2
(1 + \cos^2 \th ) d \Om
\tag{37}
\]
が得られる。もしどこか地球以外の惑星の大気が超伝導物質の粒子の分布で構成されているとすれば、その惑星の住人はおそらく青い空と赤みがかった夕焼けを享受することはできないでしょう。
つぎに、さらに想像力を膨らませて、ディスクの重ね合わせを考えよう。ここで、各ディスクは量子状態にあり、量子ホール効果を表示しているものとする。2次元の量子ホールの滴(しずく、droplet)において、カレントの期待値は
\[
\bra J_i (x) \ket = \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \ep_{ijk} \hat{n}_k F_{0j} (x)
\tag{38}
\]
で与えられる。ただし、$\hat{n}_k$は滴表面にたいする単位法線ベクトル、$\nu$は充填率である。これより、
\[
\bra J_i (x) J_j (y) \ket = \frac{e^2 \nu}{2 \pi} e_{ijk} \hat{n}_k ~ \d_0
\del^{(4)} ( x -y)
\tag{39}
\]
となる。よって、散乱振幅は
\begin{eqnarray}
\A &=& i \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \int d^4 x \om^\prime
\frac{( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} }
{\sqrt{2 \om V 2 \om^\prime V}} \, e^{-i ( k - k^\prime ) x }
\\
&=& i \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \om^\prime
\frac{( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} }
{\sqrt{2 \om V 2 \om^\prime V}} F ( \vec{q} ) 2 \pi
\del ( \om - \om^\prime )
\tag{40}
\end{eqnarray}
となる。これより微分断面積
\[
d \si = \left( \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \right)^2 \frac{\om^2}{ 16 \pi^2 }
\, |F ( \vec{q} ) |^2 |( \vec{\ep} \times \vec{\ep}^\prime ) \cdot \hat{n} |^2
\tag{41}
\]
を得る。偏光について和をとり、平均化すると
\[
d \si = \left( \frac{e^2 \nu}{2 \pi} \right)^2 \frac{\om^2}{ 32 \pi^2 }
\, |F ( \vec{q} ) |^2 \left[
\frac{( \vec{k} \cdot \hat{n} )^2 \om^2 +( \vec{k}^\prime \cdot \hat{n} )^2 \om^2 + [( \vec{k} \times \vec{k}^\prime ) \cdot \hat{n} ]^2}{\om^4}
\right]
\tag{42}
\]
となる。散乱断面積は振動数についてより緩やか、つまり$\om^2$の依存性を持つ。構造因子$F( \vec{q} )$はいつものように量子ホール滴の分布の情報から決まる。ディスクが$z$軸方向に重なりあっているとし $n$ 番目のディスクの $z$ 座標を $z_n$ とすると、量子ホール滴は$(x,y)$-平面に広がっているので、構造因子は
\[
F( \vec{q}) = \int_{\rm disk} d^2 x ~ e^{i q_1 x + i q_2 y} \sum_{n}
e^{i q_3 z_n}
\tag{43}
\]
と書ける。ディスクの幾何学的な変形の効果は、一般的な場合のこの$F(\vec{q})$を用いて簡単に評価できる。
参考文献
1. 例えば、J. Kogut and K. Wilson, Phys. Rep. 12, 75 (1974); J. Zinn-Justin, Quantum Field Theory and Critical Phenomena (Oxford University Press, 2002). を参照されたい。
2. R. Rattazzi, V.S. Rychkov, E. Tonni and A. Vichi, JHEP 0812:031 (2008); S. Rychkov, arXiv:1111.2115 (http://arxiv.org/abs/1111.2115); S. El-Showk et al, Phys. Rev. D86, 025022 (2012); J. Stat. Phys. 157, 869 (2014).
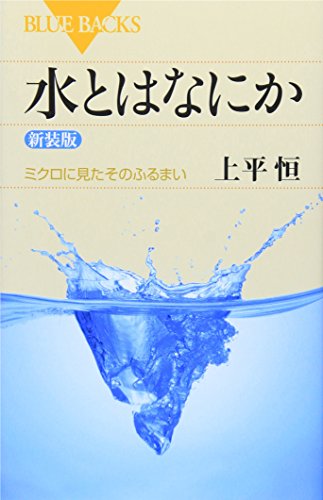
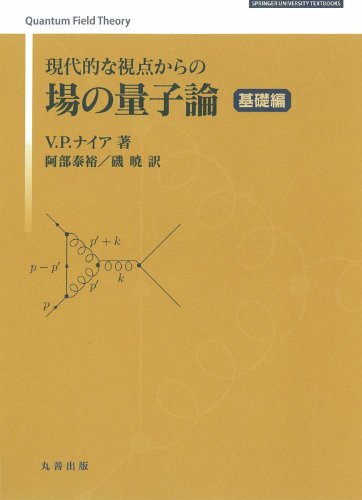
0 件のコメント:
コメントを投稿