ナイアの最近の教科書は学部生に行った標準模型の講義をまとめたものです。
S = -m \int d s = -m \int \sqrt{G_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu }
\tag{1}
\]
S = -m \int d \tau \sqrt{G_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu }
\tag{2}
\]
粒子の経路 $x^\mu (\tau)$ は $\tau$ による1次元世界から時空間への写像とみなすことができる。ここで、この1次元世界(世界線)上の計量を導入して
\[
ds = g_{ab} d \xi^a d \xi^b = g d \tau d \tau
\tag{3}
\]
ここまでの準備により点粒子から弦への一般化も簡単に行えることが分かる。時空間における点粒子の軌跡は1次元となるので、それをパラメータ化するには1変数 $\tau$ で充分である。しかし、弦は空間的に広がっているので時空間において2次元の表面つまり世界線ではなく世界面を掃く。したがって、2つの世界座標 $\xi^0 = \tau$ と $\xi^1 = \si$ が必要となる。作用は
\[
S = - \frac{M^2}{2} \int d V G_{\mu \nu} (X) g^{ab}
\frac{\d X^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}
\tag{6}
\]
内容については場の理論の教科書と重複するものばかりだし、日本から注文すると高いので買わずにいましたがやはり何が書いてあるのか気になって半年ほど前に購入しました。その後、ざっと目を通しただけで放っておいたのですが先日また手に取ってみると私が博士課程の時に知りたかった弦理論についてのナイアのコメントが最後に載っていたので以下に(無断になりますが)一部翻訳します。私が博士課程の時は弦理論真っ盛りでブレイン動力学やAdS/CFT対応などのトッピックが精力的に研究されていて私も直接論文を読んでなんとか理解に努めましたが、指導教官のナイアは弦理論とは距離をおいた研究を行っていたので先生が弦理論についてどう考えているか興味を持っていました。何度か直接質問することもありましたが、当時の流行のトッピックよりもChern-Simons理論や2次元共形場理論のWess-Zumino-Witten模型について詳しく教えてもらうことが多かった気がします。ここで紹介するナイアのコメントは体験的にも貴重なものなので日本語にして残しておくことにしました。式番号などは読みやすいように変更してあります。内容は標準的なものですが、弦理論やその他の量子重力理論についての概略を知りたい学部生や大学院生の参考になればと思います。翻訳部分は原文の292-297ページに対応します。原文が気になる方は上記の教科書をぜひ直接手に取ってみてください。
弦理論その他について
これまでの議論では粒子つまり点粒子の伝播と相互作用によって様々な現象が観測されることを見てきた。一般的な時空間上にある質量 $m$ の点粒子の作用は
\[S = -m \int d s = -m \int \sqrt{G_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu }
\tag{1}
\]
で表される。ここで、$G_{\mu\nu}$ は時空間の計量テンソルである。時空間上の経路を実数 $\tau$ で媒介表示し、$dx^\mu = \dot{x}^\mu d \tau$(ただし、$\dot{x}^\mu = dx^\mu / d \tau$)とおくこともできる。
\[S = -m \int d \tau \sqrt{G_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu }
\tag{2}
\]
粒子の経路 $x^\mu (\tau)$ は $\tau$ による1次元世界から時空間への写像とみなすことができる。ここで、この1次元世界(世界線)上の計量を導入して
\[
ds = g_{ab} d \xi^a d \xi^b = g d \tau d \tau
\tag{3}
\]
で表そう。いまは1つの座標しかない($\xi^1 = \tau$)ので、計量は上記のように書ける。つぎに作用
\begin{eqnarray}
S &=& - \hf \int d \tau \sqrt{g} \left[ G_{\mu\nu} g^{-1}
\frac{dx^\mu}{d \tau} \frac{dx^\nu}{d \tau} + m^2 \right]
\\
&=& - \hf \int d \tau \sqrt{g} \left[ G_{\mu\nu} g^{ab}
\frac{\d x^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d x^\nu}{\d \xi^b} + m^2 \right]
\tag{4}
\end{eqnarray}
S &=& - \hf \int d \tau \sqrt{g} \left[ G_{\mu\nu} g^{-1}
\frac{dx^\mu}{d \tau} \frac{dx^\nu}{d \tau} + m^2 \right]
\\
&=& - \hf \int d \tau \sqrt{g} \left[ G_{\mu\nu} g^{ab}
\frac{\d x^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d x^\nu}{\d \xi^b} + m^2 \right]
\tag{4}
\end{eqnarray}
を考えよう。$g$ の運動方程式を用いると $m^2 g = G_{\mu\nu} \dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ が得られ、これより (4)式の作用 $S$ は (2)式の作用に変形できる。その意味で (4)式の2段目の式は冗長であるが、これは一般化の可能性を示唆するものである。$G_{\mu\nu} = -\del_{\mu\nu}$ とし平坦なユークリッド時空間を考えると、(4)式の作用は
\[
S = \hf \int dV g^{ab} \frac{\d x^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d x^\nu}{\d \xi^b}
- \frac{m^2}{2} \int d V
\tag{5}
\]
と書ける。ただし、$dV = \sqrt{g} d \tau$ は「世界体積」である。(正確には、ここでは1次元なので「世界長さ」に過ぎない。)この作用の第一項は($\tau$の関数としての)$x^\mu$を場とする曲がった時空上の1次元場の理論のような形をしている。結局のところ、世界座標 $\tau$ は粒子の経路を表示する1つのパラメータに過ぎないので $\tau$ の関数である他のパラメータ $\tilde{\tau}$ を用いても問題ない。この変換 $\tau \rightarrow \tilde{\tau} = f( \tau )$ は世界長さ上の座標変換を与える。作用(5)は座標変換について不変である形で書かれている。というのも、$g_{ab}$ も一緒に変換できるからである。したがって、$\tau$ の再定義のもとでの不変性はすでに埋め込まれている。一般の曲がった時空間では適当な $G_{\mu\nu}$ を含めなければならないが、一般の $G_{\mu\nu}$ が入っている作用(4) は世界線の座標変換と時空間の座標変換のもとで不変である。また、(4) あるいは (5) で $m=0$ とおけるので質量ゼロの点粒子も簡単に記述できることにも注意しよう。
S = \hf \int dV g^{ab} \frac{\d x^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d x^\nu}{\d \xi^b}
- \frac{m^2}{2} \int d V
\tag{5}
\]
と書ける。ただし、$dV = \sqrt{g} d \tau$ は「世界体積」である。(正確には、ここでは1次元なので「世界長さ」に過ぎない。)この作用の第一項は($\tau$の関数としての)$x^\mu$を場とする曲がった時空上の1次元場の理論のような形をしている。結局のところ、世界座標 $\tau$ は粒子の経路を表示する1つのパラメータに過ぎないので $\tau$ の関数である他のパラメータ $\tilde{\tau}$ を用いても問題ない。この変換 $\tau \rightarrow \tilde{\tau} = f( \tau )$ は世界長さ上の座標変換を与える。作用(5)は座標変換について不変である形で書かれている。というのも、$g_{ab}$ も一緒に変換できるからである。したがって、$\tau$ の再定義のもとでの不変性はすでに埋め込まれている。一般の曲がった時空間では適当な $G_{\mu\nu}$ を含めなければならないが、一般の $G_{\mu\nu}$ が入っている作用(4) は世界線の座標変換と時空間の座標変換のもとで不変である。また、(4) あるいは (5) で $m=0$ とおけるので質量ゼロの点粒子も簡単に記述できることにも注意しよう。
ここまでの準備により点粒子から弦への一般化も簡単に行えることが分かる。時空間における点粒子の軌跡は1次元となるので、それをパラメータ化するには1変数 $\tau$ で充分である。しかし、弦は空間的に広がっているので時空間において2次元の表面つまり世界線ではなく世界面を掃く。したがって、2つの世界座標 $\xi^0 = \tau$ と $\xi^1 = \si$ が必要となる。作用は
\[
S = - \frac{M^2}{2} \int d V G_{\mu \nu} (X) g^{ab}
\frac{\d X^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}
\tag{6}
\]
と取れる。ここで、$a, \, b$ は 0, 1 の値をとり $dV = \sqrt{g} d \tau d \si$ である。また、時空間座標として大文字の$X$を用いた。$X$ は質量の逆数の次元を持つので、係数として質量の2乗の因子があれば作用は次元ゼロとなる。ここではこの因子を $M^2$ とおいた。この作用において $g^{ab}$ の変分をとると世界面の計量についての運動方程式
\[
G_{\mu\nu} \frac{\d X^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}
- \hf G_{\mu\nu} g^{cd}
\frac{\d X^\mu}{\d \xi^c} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^d}
g_{ab} \, = \, 0
\tag{7}
\]
が得られる。簡単のため $ G_{\mu\nu} = - \del_{\mu\nu} $ とし、この方程式から $g_{ab}$ の行列式を計算すると、作用(6)は
\[
S = M^2 \int d \tau d \si \sqrt{\det ( \d_a X^\mu \d_b X_\mu ) }
\tag{8}
\]
と変形できる。被積分関数は $( \tau , \si )$ から2つの時空間座標への座標変換のヤコビアンである。したがって、この作用は弦が時空間において時間発展したときの変位面の面積に $M^2$ をかけたものである。これは明らかに(1)でみた点粒子の時空間における経路長さを一般化したものになっている。(これより弦の場合は $m^2$ のような項を追加する必要がないことも分かる。)
弦理論の基本的なアイデアは点粒子の概念を弦に置き換えることであり、このとき弦のダイナミクスは作用(6)で与えられる。面積の形であらわされる作用(8)は南部-後藤作用として呼ばれる。一方、(6)の形はポリヤコフの作用として知られている。後者のほうを採用すると弦のダイナミクスを世界面上の2次元場の理論とみなすことができる。ただし、$X^\mu ( \xi ) = X^\mu ( \tau , \si )$ を場の演算子とする。すると、場の理論の無数のテクニックを投入して弦理論の解析を行うことができる。$\xi^0 = \tau$, $\xi^1 = \si$ をそれぞれ2次元世界面の「時間座標」、「空間座標」とおける。さらに、$\si$ を線分上あるいは円のような閉曲線上に置くこともできる。つまり、一般的には開いた弦と閉じた弦が存在する。
弦の作用(6)は他にも重要な特性を持つ。すなわち、局所的なスケール変換不変性である。関係式
\[
S[ X , \tilde{g}_{ab} \equiv e^{\phi} g_{ab} ] \, = \, S [X ,g_{ab} ]
\tag{9}
\]
に注意しよう。ただし、$\sqrt{\det \tilde{g}} = e^{\phi} \sqrt{\det g}$, $\tilde{g}^{ab} = e^{-\phi} g^{ab}$ であり、$\phi$ は $\xi$ の任意の関数である。この関係は2次元特有のものである。(9)で与えられる理論は局所場の理論のみなせるので、局所的なスケール不変性から理論の共変不変性が導かれる。
$g_{ab}$ の運動方程式すなわち(7)式より弦のダイナミクスは世界面の計量とは独立しているであろうことがわかる。したがって、$\si$ にある基準幅を課すことができる。慣例的に開弦の場合は $\si$ を $[ 0 , \pi ]$ にとり閉弦の場合は $[ 0 , 2 \pi ]$ とし条件 $X^\mu ( \tau , 0 ) = X^\mu ( \tau , 2 \pi )$ を課す。これにより $X^\mu ( \tau , \si )$ を $\si$ の定義域におけるモードの完全系で展開することができる。各モードは実用上は点粒子のように振舞う。よって、1つの弦は異なる質量をもつ無数の点粒子の集団としてとらえることができ、このとき質量のスケールは(6)式の $M$ で与えられる。超弦理論においては最低質量はゼロとなり、それより大きな質量は $M$ の倍数となる。このパラメータ $M$ は通常プランク質量 $M_{Pl} \sim 10^{19}$ GeV で与えられる。そのため、スピン2の無質量粒子でその相互作用が $M$ で支配されるものを重力子と同定することができる。他の無質量粒子についても我々の知っている粒子に同定することができれば、弦理論の低エネルギー近似として標準模型の結果の多くが再現できるのではないかと期待される。標準模型の粒子はゼロでない質量を持つが、それらは自発的な対称性の破れによって理解できるというアイデアである。これらの質量は $M_{Pl} \sim 10^{19}$ GeV と比べると微小なので、対称性が破れる以前の質量をゼロから始めることは理にかなった状況である。とはいうものの、これまでの所このシナリオに沿った現象論的に満足のいく結果は得られていない。弦理論を完成させるには複数弦の配位や弦の生成消滅の可能性を考慮する必要がある。これはスカラー場やゲージ場を考え、それらの場の理論の作用(この作用は世界線の作用(1)とは異なる)から伝播関数や頂点演算子を導いて多粒子系のダイナミクスを記述することに類似している。つまり、「弦の場の理論」が必要となる。ここではそのような理論をどのように構成するかについては触れないが、以下に弦理論の物理についてもう少し考察してみよう。
先に触れた2次元共形不変性はとても重要である。この対称性を用いると、全空間の中で相互作用をする弦の理論が量子論において重要な要請であるユニタリー性をもつことを示すことができる。しかし、一般的には、スケール不変性を場の理論中で保つことは難しい。というのも、繰り込みの処方を行う際には運動量の積分にカットオフを導入する必要があり、そのようなカットオフは共変不変性を破るためである。よって、2次元場の理論として作用(6)をみると、そのような問題が生じる。つまり、共形変換のもので量子論が不変にならない。しかしながら、超対称性をもつ理論を考え、時空間の次元を適切に選ぶと量子論においてもスケール不変性を保つことができる。これは超対称性によって様々な巧妙な相殺が起こるためである。このようなことが起こる最も簡単な場合は10次元時空上の超対称性理論である。現実の4次元世界は我々にとってアクセス可能な次元と解釈され、残りの次元は非常な高エネルギー状態でない限りアクセス不能な微小コンパクト多様体に閉じ込められているとみなす。あるいは、我々は10次元時空間に埋め込まれた4次元の壁にいると解釈する。このようなシナリオの賛否についてはこれまでに数多く議論されてきた。いうまでもなく、完全に満足いくモデルはまだ見つかっていない。
良い面について言えば、弦のモードの中に重力子のようなスピン2の粒子があるため、弦理論を用いて重力の量子理論を矛盾なく構築できる可能性がある。さらに、弦の場の理論が分からなくても、世界面の作用(6)を用いて摂動論として散乱振幅を計算することができる。世界面を一般的な2次元多様体とみなすと、球面上の計算からツリーレベルの古典的な結果が得られる。また、(種数1の)トーラス上の計算から1-ループの量子効果、種数2の多様体(球面に2つのハンドルが付いたもの)からは2-ループの量子効果などの計算ができる。例えば、重力子は時空計量の微小変形とみなせるので、作用(6)に $G_{\mu \nu} \approx \eta_{\mu \nu} + h_{\mu \nu} (X)$ を代入すると、$S$ は平坦時空の作用に補正項 $- \frac{M^2}{2} \int d V h_{\mu \nu} (x) g^{ab} \frac{ \d X^\mu}{ \d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}$ を加えたものになる。球面上でのこのような項の積を考え、(2次元場の理論の意味で)その平均を取ると、ツリーレベルの重力子散乱振幅が得られる。同様にして、トーラス上での平均から1-ループの散乱振幅が求められ、2-ループ以上について同じように計算できる。この手法は例えばユニタリー性のチェックなど弦理論の正さをテストするのに大きな成功を収めた。
非摂動論的には、状況はより困難である。弦理論には、1990年代には明らかになったのであるが、様々な次元の膜(メンブレイン)のような拡張された物体も含まれなければならず、これらは正に非摂動的な構造物である。そのような膜のダイナミクスを解析することによって自由度の微視的な数え上げを行うことが可能になり、ブラックホールのエントロピー公式を、少なくとも超対称性を持つ場合に限り、説明することができるようになった。また、すべての無矛盾な弦理論は、M理論と名付けられた11次元の統一理論のある特別なケースあるいは特別なコンパクト化で説明づくことが強く示唆されている。このM理論はまたその低エネルギー極限の1つとして11次元の超対称重力理論を含むことが知られている。
このように、弦理論は数多くの豊富な結果だけでなく多くの問題について新しい視点を我々に提供している。また弦理論は場の理論の伝統的な問題にも光を当てている。例えば、弦理論のテクニックはゲージ理論に出てくる大量のファインマン図の和を効率よく計算するのに役立っている。しかしながら、計量それ自体が量子揺らぎを受ける重力の量子論において、作用(6)のように時空間の計量を用いて弦理論を形式化するのは概念的に満足いくものではないことに注意しよう。この作用は球面やトーラス上での摂動計算にも用いられるものである。そのため弦理論の異なる形式化を図るのは自然のことであろう。マルダセナ予想(AdS/CFT対応)では5次元の AdS$(\times S^5$) 上のIIB型超弦理論と(AdS空間の境界として現れる)ミンコフスキ空間上で超対称性を最大限に持つヤン-ミルズ理論(これは ${\cal N}=4$ ヤン-ミルズ理論であり、共形場の理論である)とを同定しているが、この予想は弦理論の異なる形式化の1つであり、(ある特定の背景のもとではあるものの)弦理論をヤン-ミルズ理論で実質的に定義している。このような双対性を用いたホログラフィックな手法は様々な物理現象に応用され、いまや物性物理の世界にまで浸透しており、物理過程の理解へ全く新しいパラダイムを提供している。
弦理論の分野は今では充分に発展しており、多くの分厚い教科書が書かれているが実験による裏付けを得られるにはまだほど遠い段階にある。ここでの短いコメントは鍵穴から覗いた概観に過ぎない。下記の参考文献などからより包括的な理解を得てもらいたい。
量子重力については弦理論以外にも多くの提案がなされている。その中でも広く研究されている代替案としてループ量子重力と非可換幾何学がある。ループ量子重力は標準的なアインシュタインの重力理論を非アーベル型ゲージ理論に現れる変数に類似したものを用いて形式化しようとするアシュテカ (Ashtekar) による試みである。これらの変数はアシュテカ変数と呼ばれ、この形式化によると時空をループのネットワークとして解釈する描像が自然に導かれる。ただし、ここでのループは$SU(2)$群の要素でラベルされるものである。この理論における観測量についても詳細な研究が行われており、一般的な特性として、ブラックホールからの放射とエントロピーのベケンスイタイン-ホーキングの面積則が導かれている。
多様体とその幾何学をその多様体上で定義される関数の代数から再構成することができる。この結果はフォン・ノイマンにまで遡るものである。アラン・コンヌはこれを関数の代数がある条件を満たす非可換代数である場合にまで拡張し、非可換幾何学を定義できることを示した。必要な情報は観測量の代数${\cal A}$、一連のヒルベルト空間${\cal H}$、そして抽象的に定義されたディラック演算子${\cal D}$である。ここで、${\cal D}$は計量についての情報をもつ。(物理系のヒルベルト空間は対応する古典系の相空間を量子化したものである。相空間は滑らかな多様体であり、それをヒルベルト空間で置き換えることが量子化のエッセンスである。)これらのスペクトル・トリプル $( {\cal A},{\cal H},{\cal D} )$ を用いて重力を形式化できる。これは量子重力への別の手法を提供するものであり、精力的に調査されている。非可換幾何学で表される空間は弦理論の特別な場合にも出てくるので、これらの手法には弦理論に基づくアプローチと重複する部分があるかもしれない。
これらのアプローチに共通するテーマは時空間それ自体が創発される概念であるというものである。つまり、なにか基礎となるダイナミクスの粗視化された領域における好都合な対象物として時空間が現れる。そのため、重力自体は微細スケールの時空間においては徐々に消え失せてしまう現象として解釈できる。こういった側面に焦点を当てた解析はこれまでに数多くなされており、背後にあるダイナミクスとは独立した重力の一般的な性質を理解しようとする努力が払われている。
1. 弦理論に関する標準的なものは M.B. Green, J.H. Schwarz and E. Witten, Superstring theory, Vols 1 and 2, Cambridge University Press (1987); J. Polchinski, String theory, Vols 1 and 2, Cambridge University Press (2001 and 2005). これ以外のものとして、例えば、M. Dine, Supersymmetry and string theory: Beyond the Standard Model, Cambridge University Press (2007); K. Becker, M. Becker and J.H. Schwarz, String theory and M-theory: A modern introduction, Cambridge University Press (2007) がある。
4. 非可換幾何学と重力については以下の文献を参照されたい。A. Connes, Noncommutative geometry, Academic Press (1994); J. Madore, An Introduction to Noncommutative Differential Geometry and its Physical Applications, Cambridge University Press (1995); G. Landi, An Introduction to Noncommutative Spaces and Their Geometries, Lecture Notes in Physics Monographs (Book 51), springer (1997); A. Schenkel, Noncommutative gravity and quantum field theory on noncommutative curved spacetimes, arXiv:1210.1115 [math-ph]. 重力に関係するその他の文献としては以下のものがある。D. Kastler, Commun. Math. Phys. 166, 633 (1995); A. Connes, Commun. Math. Phys. 182, 155 (1996); A.H. Chamseddine and A. Connes, Phys. Rev. Lett. 77, 4868 (1996); A.H. Chamseddine, Commun. Math. Phys. 186, 731 (1997).
\[
G_{\mu\nu} \frac{\d X^\mu}{\d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}
- \hf G_{\mu\nu} g^{cd}
\frac{\d X^\mu}{\d \xi^c} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^d}
g_{ab} \, = \, 0
\tag{7}
\]
が得られる。簡単のため $ G_{\mu\nu} = - \del_{\mu\nu} $ とし、この方程式から $g_{ab}$ の行列式を計算すると、作用(6)は
\[
S = M^2 \int d \tau d \si \sqrt{\det ( \d_a X^\mu \d_b X_\mu ) }
\tag{8}
\]
と変形できる。被積分関数は $( \tau , \si )$ から2つの時空間座標への座標変換のヤコビアンである。したがって、この作用は弦が時空間において時間発展したときの変位面の面積に $M^2$ をかけたものである。これは明らかに(1)でみた点粒子の時空間における経路長さを一般化したものになっている。(これより弦の場合は $m^2$ のような項を追加する必要がないことも分かる。)
弦理論の基本的なアイデアは点粒子の概念を弦に置き換えることであり、このとき弦のダイナミクスは作用(6)で与えられる。面積の形であらわされる作用(8)は南部-後藤作用として呼ばれる。一方、(6)の形はポリヤコフの作用として知られている。後者のほうを採用すると弦のダイナミクスを世界面上の2次元場の理論とみなすことができる。ただし、$X^\mu ( \xi ) = X^\mu ( \tau , \si )$ を場の演算子とする。すると、場の理論の無数のテクニックを投入して弦理論の解析を行うことができる。$\xi^0 = \tau$, $\xi^1 = \si$ をそれぞれ2次元世界面の「時間座標」、「空間座標」とおける。さらに、$\si$ を線分上あるいは円のような閉曲線上に置くこともできる。つまり、一般的には開いた弦と閉じた弦が存在する。
弦の作用(6)は他にも重要な特性を持つ。すなわち、局所的なスケール変換不変性である。関係式
\[
S[ X , \tilde{g}_{ab} \equiv e^{\phi} g_{ab} ] \, = \, S [X ,g_{ab} ]
\tag{9}
\]
に注意しよう。ただし、$\sqrt{\det \tilde{g}} = e^{\phi} \sqrt{\det g}$, $\tilde{g}^{ab} = e^{-\phi} g^{ab}$ であり、$\phi$ は $\xi$ の任意の関数である。この関係は2次元特有のものである。(9)で与えられる理論は局所場の理論のみなせるので、局所的なスケール不変性から理論の共変不変性が導かれる。
$g_{ab}$ の運動方程式すなわち(7)式より弦のダイナミクスは世界面の計量とは独立しているであろうことがわかる。したがって、$\si$ にある基準幅を課すことができる。慣例的に開弦の場合は $\si$ を $[ 0 , \pi ]$ にとり閉弦の場合は $[ 0 , 2 \pi ]$ とし条件 $X^\mu ( \tau , 0 ) = X^\mu ( \tau , 2 \pi )$ を課す。これにより $X^\mu ( \tau , \si )$ を $\si$ の定義域におけるモードの完全系で展開することができる。各モードは実用上は点粒子のように振舞う。よって、1つの弦は異なる質量をもつ無数の点粒子の集団としてとらえることができ、このとき質量のスケールは(6)式の $M$ で与えられる。超弦理論においては最低質量はゼロとなり、それより大きな質量は $M$ の倍数となる。このパラメータ $M$ は通常プランク質量 $M_{Pl} \sim 10^{19}$ GeV で与えられる。そのため、スピン2の無質量粒子でその相互作用が $M$ で支配されるものを重力子と同定することができる。他の無質量粒子についても我々の知っている粒子に同定することができれば、弦理論の低エネルギー近似として標準模型の結果の多くが再現できるのではないかと期待される。標準模型の粒子はゼロでない質量を持つが、それらは自発的な対称性の破れによって理解できるというアイデアである。これらの質量は $M_{Pl} \sim 10^{19}$ GeV と比べると微小なので、対称性が破れる以前の質量をゼロから始めることは理にかなった状況である。とはいうものの、これまでの所このシナリオに沿った現象論的に満足のいく結果は得られていない。弦理論を完成させるには複数弦の配位や弦の生成消滅の可能性を考慮する必要がある。これはスカラー場やゲージ場を考え、それらの場の理論の作用(この作用は世界線の作用(1)とは異なる)から伝播関数や頂点演算子を導いて多粒子系のダイナミクスを記述することに類似している。つまり、「弦の場の理論」が必要となる。ここではそのような理論をどのように構成するかについては触れないが、以下に弦理論の物理についてもう少し考察してみよう。
先に触れた2次元共形不変性はとても重要である。この対称性を用いると、全空間の中で相互作用をする弦の理論が量子論において重要な要請であるユニタリー性をもつことを示すことができる。しかし、一般的には、スケール不変性を場の理論中で保つことは難しい。というのも、繰り込みの処方を行う際には運動量の積分にカットオフを導入する必要があり、そのようなカットオフは共変不変性を破るためである。よって、2次元場の理論として作用(6)をみると、そのような問題が生じる。つまり、共形変換のもので量子論が不変にならない。しかしながら、超対称性をもつ理論を考え、時空間の次元を適切に選ぶと量子論においてもスケール不変性を保つことができる。これは超対称性によって様々な巧妙な相殺が起こるためである。このようなことが起こる最も簡単な場合は10次元時空上の超対称性理論である。現実の4次元世界は我々にとってアクセス可能な次元と解釈され、残りの次元は非常な高エネルギー状態でない限りアクセス不能な微小コンパクト多様体に閉じ込められているとみなす。あるいは、我々は10次元時空間に埋め込まれた4次元の壁にいると解釈する。このようなシナリオの賛否についてはこれまでに数多く議論されてきた。いうまでもなく、完全に満足いくモデルはまだ見つかっていない。
良い面について言えば、弦のモードの中に重力子のようなスピン2の粒子があるため、弦理論を用いて重力の量子理論を矛盾なく構築できる可能性がある。さらに、弦の場の理論が分からなくても、世界面の作用(6)を用いて摂動論として散乱振幅を計算することができる。世界面を一般的な2次元多様体とみなすと、球面上の計算からツリーレベルの古典的な結果が得られる。また、(種数1の)トーラス上の計算から1-ループの量子効果、種数2の多様体(球面に2つのハンドルが付いたもの)からは2-ループの量子効果などの計算ができる。例えば、重力子は時空計量の微小変形とみなせるので、作用(6)に $G_{\mu \nu} \approx \eta_{\mu \nu} + h_{\mu \nu} (X)$ を代入すると、$S$ は平坦時空の作用に補正項 $- \frac{M^2}{2} \int d V h_{\mu \nu} (x) g^{ab} \frac{ \d X^\mu}{ \d \xi^a} \frac{\d X^\nu}{\d \xi^b}$ を加えたものになる。球面上でのこのような項の積を考え、(2次元場の理論の意味で)その平均を取ると、ツリーレベルの重力子散乱振幅が得られる。同様にして、トーラス上での平均から1-ループの散乱振幅が求められ、2-ループ以上について同じように計算できる。この手法は例えばユニタリー性のチェックなど弦理論の正さをテストするのに大きな成功を収めた。
非摂動論的には、状況はより困難である。弦理論には、1990年代には明らかになったのであるが、様々な次元の膜(メンブレイン)のような拡張された物体も含まれなければならず、これらは正に非摂動的な構造物である。そのような膜のダイナミクスを解析することによって自由度の微視的な数え上げを行うことが可能になり、ブラックホールのエントロピー公式を、少なくとも超対称性を持つ場合に限り、説明することができるようになった。また、すべての無矛盾な弦理論は、M理論と名付けられた11次元の統一理論のある特別なケースあるいは特別なコンパクト化で説明づくことが強く示唆されている。このM理論はまたその低エネルギー極限の1つとして11次元の超対称重力理論を含むことが知られている。
このように、弦理論は数多くの豊富な結果だけでなく多くの問題について新しい視点を我々に提供している。また弦理論は場の理論の伝統的な問題にも光を当てている。例えば、弦理論のテクニックはゲージ理論に出てくる大量のファインマン図の和を効率よく計算するのに役立っている。しかしながら、計量それ自体が量子揺らぎを受ける重力の量子論において、作用(6)のように時空間の計量を用いて弦理論を形式化するのは概念的に満足いくものではないことに注意しよう。この作用は球面やトーラス上での摂動計算にも用いられるものである。そのため弦理論の異なる形式化を図るのは自然のことであろう。マルダセナ予想(AdS/CFT対応)では5次元の AdS$(\times S^5$) 上のIIB型超弦理論と(AdS空間の境界として現れる)ミンコフスキ空間上で超対称性を最大限に持つヤン-ミルズ理論(これは ${\cal N}=4$ ヤン-ミルズ理論であり、共形場の理論である)とを同定しているが、この予想は弦理論の異なる形式化の1つであり、(ある特定の背景のもとではあるものの)弦理論をヤン-ミルズ理論で実質的に定義している。このような双対性を用いたホログラフィックな手法は様々な物理現象に応用され、いまや物性物理の世界にまで浸透しており、物理過程の理解へ全く新しいパラダイムを提供している。
弦理論の分野は今では充分に発展しており、多くの分厚い教科書が書かれているが実験による裏付けを得られるにはまだほど遠い段階にある。ここでの短いコメントは鍵穴から覗いた概観に過ぎない。下記の参考文献などからより包括的な理解を得てもらいたい。
量子重力については弦理論以外にも多くの提案がなされている。その中でも広く研究されている代替案としてループ量子重力と非可換幾何学がある。ループ量子重力は標準的なアインシュタインの重力理論を非アーベル型ゲージ理論に現れる変数に類似したものを用いて形式化しようとするアシュテカ (Ashtekar) による試みである。これらの変数はアシュテカ変数と呼ばれ、この形式化によると時空をループのネットワークとして解釈する描像が自然に導かれる。ただし、ここでのループは$SU(2)$群の要素でラベルされるものである。この理論における観測量についても詳細な研究が行われており、一般的な特性として、ブラックホールからの放射とエントロピーのベケンスイタイン-ホーキングの面積則が導かれている。
多様体とその幾何学をその多様体上で定義される関数の代数から再構成することができる。この結果はフォン・ノイマンにまで遡るものである。アラン・コンヌはこれを関数の代数がある条件を満たす非可換代数である場合にまで拡張し、非可換幾何学を定義できることを示した。必要な情報は観測量の代数${\cal A}$、一連のヒルベルト空間${\cal H}$、そして抽象的に定義されたディラック演算子${\cal D}$である。ここで、${\cal D}$は計量についての情報をもつ。(物理系のヒルベルト空間は対応する古典系の相空間を量子化したものである。相空間は滑らかな多様体であり、それをヒルベルト空間で置き換えることが量子化のエッセンスである。)これらのスペクトル・トリプル $( {\cal A},{\cal H},{\cal D} )$ を用いて重力を形式化できる。これは量子重力への別の手法を提供するものであり、精力的に調査されている。非可換幾何学で表される空間は弦理論の特別な場合にも出てくるので、これらの手法には弦理論に基づくアプローチと重複する部分があるかもしれない。
これらのアプローチに共通するテーマは時空間それ自体が創発される概念であるというものである。つまり、なにか基礎となるダイナミクスの粗視化された領域における好都合な対象物として時空間が現れる。そのため、重力自体は微細スケールの時空間においては徐々に消え失せてしまう現象として解釈できる。こういった側面に焦点を当てた解析はこれまでに数多くなされており、背後にあるダイナミクスとは独立した重力の一般的な性質を理解しようとする努力が払われている。
参考文献
1. 弦理論に関する標準的なものは M.B. Green, J.H. Schwarz and E. Witten, Superstring theory, Vols 1 and 2, Cambridge University Press (1987); J. Polchinski, String theory, Vols 1 and 2, Cambridge University Press (2001 and 2005). これ以外のものとして、例えば、M. Dine, Supersymmetry and string theory: Beyond the Standard Model, Cambridge University Press (2007); K. Becker, M. Becker and J.H. Schwarz, String theory and M-theory: A modern introduction, Cambridge University Press (2007) がある。
2. AdS/CFT対応の原論文は J. Maldacena, Adv. Theor. Math. Phys. 2, 231 (1998), arXiv:hep-th/9711200. AdS/CFT対応とその応用については多くの論文で研究されている。最近のレビューとして、例えば以下の文献を参照されたい。J. Maldacena, TASI 2003 Lectures on AdS/CFT, arXiv:hep-th/0309246; H. Nastase, Introduction to AdS/CFT correspondence, Cambridge University Press (2015); M. Natsuume, AdS/CFT Duality User Guide, Lecture Notes in Physics 9150, Springer Japan (2015); L. Susskind and J. Lindesay, An introduction to black holes, information and the string theory revolution: The holographic universe, World Scientific (2005).
3. ループ量子重力のレビューとしては以下の文献を参照されたい。A. Ashtekar, http://www.scholarpedia.org/article/Ashtekar_variables; A. Ashtekar and J. Lewandowski, Class. Quant. Grav. 21, R53-R152 (2004); R. Gambini and J. Pullin, A First Course in Loop Quantum Gravity, Oxford University Press (2012); C. Rovelli and F. Vidotto, Covariant loop quantum gravity, Cambridge University Press (2014).4. 非可換幾何学と重力については以下の文献を参照されたい。A. Connes, Noncommutative geometry, Academic Press (1994); J. Madore, An Introduction to Noncommutative Differential Geometry and its Physical Applications, Cambridge University Press (1995); G. Landi, An Introduction to Noncommutative Spaces and Their Geometries, Lecture Notes in Physics Monographs (Book 51), springer (1997); A. Schenkel, Noncommutative gravity and quantum field theory on noncommutative curved spacetimes, arXiv:1210.1115 [math-ph]. 重力に関係するその他の文献としては以下のものがある。D. Kastler, Commun. Math. Phys. 166, 633 (1995); A. Connes, Commun. Math. Phys. 182, 155 (1996); A.H. Chamseddine and A. Connes, Phys. Rev. Lett. 77, 4868 (1996); A.H. Chamseddine, Commun. Math. Phys. 186, 731 (1997).
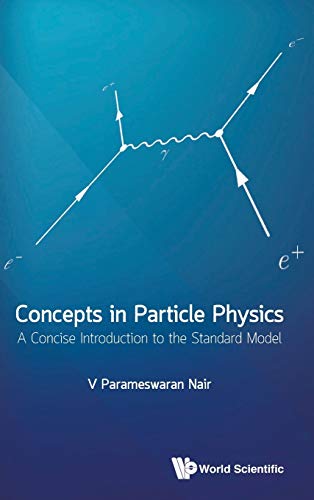
0 件のコメント:
コメントを投稿