前回のエントリー「グラスマン多様体上の超幾何関数1: 青本流の一般化」の続きです。前回は青本先生の一般化された超幾何関数のレビューを行いました。結果の羅列にならないよう、丁寧に解説したつもりですがいかがでしたでしょうか。ナイーブに考えると、多粒子系の物理現象を解析するには多変数関数を用いるのが自然なので、今後は大学の授業でも多変数関数の講義が増えるのではないでしょうか。グラスマン多様体上の超幾何関数の場合は、定義から(部分)線形空間が保証されているので量子論へもスムーズに拡張できるので物理への応用には適しているはずです。一般の多変数関数論では、最近
などの素晴らしい教科書が刊行されているので興味ある人は手に取ってみてください。ただ、単に私の理解・勉強不足なだけかもしれませんが、物理への応用という点からは抽象的すぎる印象です。
前回のエントリーで見たように一般化された超幾何関数 $F (Z)$ では定義から $F (Z)$ の満たす微分方程式が決まっているので、もし $F (Z)$ を汎関数とみなして量子系に拡張できれば、系の物理量は $F (Z)$ の積分表示から求まると解釈できます。この考えを敷衍すると多粒子系の物理ではラグランジアンやハミルトニアンから始めるのではなく、物理量を導く$S$-行列汎関数を $F (Z)$ から直接求めることができるのではないでしょうか。粒子間の相互作用はすべて $F (Z)$ を定義する微分方程式
\begin{eqnarray}
\sum_{j = 0}^{n} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{pj}} &=& - \del_{ip} F
~~~ ( 0 \le i, p \le k )
\tag{1-2} \\
\sum_{i = 0}^{k} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{ij}} &=& \al_{j} F
~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-3} \\
\frac{\d^2 F}{\d z_{ip}\d z_{jq}} &=& \frac{\d^2 F}{\d z_{iq}\d z_{jp}}
~~~ ( 0 \le i, j \le k \, ; ~ 0 \le p, q \le n )
\tag{1-4}
\end{eqnarray}
に支配されるという立場です。私が提唱しているツイスター空間上のホロノミー形式というのはこの考えを推し進めたものです。
前回のエントリーでは(ツイスト)コホモロジーとか聞きなれない用語が出てきましたが、物理の言葉ではこれは基本的にアーベル型ゲージ理論と同じことです。コホモロジー類を議論するときに出てきた共変微分
\[
\nabla \, = \, d + d \log \Phi \wedge \, = \,
d + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{ d l_j}{l_j} \wedge
\tag{1-14}
\]
がこのコホモロジーのエッセンスですがこれはゲージ理論の見方ではゲージポテンシャルとして $d \log \Phi = \frac{d \Phi}{\Phi}$ を選ぶことに対応します。最後に日本語への翻訳にあたり用語は青木・喜多先生の教科書に従いました。そのため英語の twisted は全て「ツイスト」と略されているので(とくに英語で話すときは)注意してください。それでは本題に入ります。
ここでは特に $Gr( 2, n+1)$ の場合を考察する。対応する配位空間は単に $\cp^1$ 上の相違な $n+1$ 個の点で与えられる。これは、2次元の小行列式がゼロとならない $2 \times (n+1)$ 行列 $Z$ で表される。$GL(2, \C)$-左作用としての座標変換と $H_2 = \diag(h_0, h_1)$-右作用としてのスケール変換についての不変性を課すと、$Z$ を次のように一意にパラメータ表示することができる。
\[
Z =
\left(
\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
0 & 1 & -1 & -z_3 & \cdots & -z_{n} \\
\end{array}
\right)
\tag{2-1}
\]
ただし、$z_i \ne 0 , 1, z_j$ ($i\ne j$, $3 \le i, j \le n$) である。よって、$Z$ は
\[
Z \, \simeq \, \{ (z_3 , z_4 , \cdots , z_{n} ) \in \C^{n-2} \, | \,
z_i \ne 0, 1, z_j ~ (i\ne j) \}
\tag{2-2}
\]
とみなせる。残りの3点 $(z_0 , z_1 , z_2 )$ は $\{ 0, 1, \infty \}$ に固定することができる。これは $\cp^1$ の $(n+1)$ 個の異なる点のうち3点は $GL(2, \C)$ 不変性により固定されることからも分かる。
前回のエントリーの応用として $Gr(2, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数の系統的な導出を以下に行う。まず、次のような形の多価関数から始めよう。
\[
\Phi = 1^{\al_0} \cdot t^{\al_1} ( 1 -t)^{\al_2}
(1 - z_3 t)^{\al_3} \cdots ( 1 - z_{n} t )^{\al_n} \, = \, \prod_{j=1}^{n} l_j (t)^{\al_j}
\tag{2-3}
\]
ここで、
\[
l_0(t) = 1 \, , ~ l_1(t) = t \, , ~ l_2 (t) = 1 -t
\, , ~ l_j (t) = 1 - z_{j} t ~~ (3 \le j \le n)
\tag{2-4}
\]
である。(1-5), (1-6) と同様に、指数は非整数条件
\[
\al_j \not\in \Z ~~ (0 \le j \le n)\, ,~~~ \sum_{j=0}^{n} \al_j = -2
\tag{2-5}
\]
に従う。以前考えたように、この非整数条件は (2-44)-(2-46)、つまり $F(Z)$ が $F(Z) = \int_\Del \Phi dt$ と表される場合に課される。多価関数 $\Phi$ が定義される空間は
\[
X = \cp^1 - \{ 0 ,1, 1/ z_{3} , \cdots , 1/ z_{n} , \infty \}
\tag{2-6}
\]
で与えられる。$\Phi$ から $X$ のランク1局所系 ${\cal L}$ とその双対局所系 ${\cal L}^{\vee}$ が決まる。よって、(1-50) を用いると、コホモロジー群 $H^1 ( X , {\cal L})$ の基底は
\[
d \log \frac{l_{j+1}}{l_j} ~~~~~~ (0 \le j \le n-1)
\tag{2-7}
\]
で与えられる。いまの場合、ホモロジー群 $H_1 ( X , {\cal L}^{\vee} )$ の基底は分岐点を結ぶ経路の集合で指定される。例えば、そのような基底として
\[
\Del_{\infty 0} \, , \,
\Del_{01} \, , \, \Del_{1\frac{1}{z_3}} \, , \, \Del_{\frac{1}{z_3}\frac{1}{z_4} }
\, , \, \cdots \, , \, \Del_{\frac{1}{z_{n-1}}\frac{1}{z_{n}} }
\tag{2-8}
\]
を選ぶことができる。ここで、$\Del_{pq}$ は分岐点 $p$ と $q$ を結ぶ $\cp^1$ 上の経路を示す。まとめると、(2-3)式の $\Phi$ に付随するホモロジー群の要素 $\Del \in H_1 ( X , {\cal L}^{\vee} )$ に対して、$Gr ( 2, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数の集合
\[
f_j ( Z ) \, = \, \int_\Del \Phi \, d \log \frac{l_{j+1}}{l_j}
\tag{2-9}
\]
を定義することができる。ただし、$0 \le j \le n-1$ である。1変数だけの最も簡単な場合は $n=3$ で与えられ、これはガウスの超幾何関数に相当する。次のエントリーではこの場合について考察する。
\begin{eqnarray}
\sum_{j = 0}^{n} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{pj}} &=& - \del_{ip} F
~~~ ( 0 \le i, p \le k )
\tag{1-2} \\
\sum_{i = 0}^{k} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{ij}} &=& \al_{j} F
~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-3} \\
\frac{\d^2 F}{\d z_{ip}\d z_{jq}} &=& \frac{\d^2 F}{\d z_{iq}\d z_{jp}}
~~~ ( 0 \le i, j \le k \, ; ~ 0 \le p, q \le n )
\tag{1-4}
\end{eqnarray}
に支配されるという立場です。私が提唱しているツイスター空間上のホロノミー形式というのはこの考えを推し進めたものです。
前回のエントリーでは(ツイスト)コホモロジーとか聞きなれない用語が出てきましたが、物理の言葉ではこれは基本的にアーベル型ゲージ理論と同じことです。コホモロジー類を議論するときに出てきた共変微分
\[
\nabla \, = \, d + d \log \Phi \wedge \, = \,
d + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{ d l_j}{l_j} \wedge
\tag{1-14}
\]
がこのコホモロジーのエッセンスですがこれはゲージ理論の見方ではゲージポテンシャルとして $d \log \Phi = \frac{d \Phi}{\Phi}$ を選ぶことに対応します。最後に日本語への翻訳にあたり用語は青木・喜多先生の教科書に従いました。そのため英語の twisted は全て「ツイスト」と略されているので(とくに英語で話すときは)注意してください。それでは本題に入ります。
2. $Gr(2, n+1)$ 上の超幾何関数
\[
Z =
\left(
\begin{array}{cccccc}
1 & 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\
0 & 1 & -1 & -z_3 & \cdots & -z_{n} \\
\end{array}
\right)
\tag{2-1}
\]
ただし、$z_i \ne 0 , 1, z_j$ ($i\ne j$, $3 \le i, j \le n$) である。よって、$Z$ は
\[
Z \, \simeq \, \{ (z_3 , z_4 , \cdots , z_{n} ) \in \C^{n-2} \, | \,
z_i \ne 0, 1, z_j ~ (i\ne j) \}
\tag{2-2}
\]
とみなせる。残りの3点 $(z_0 , z_1 , z_2 )$ は $\{ 0, 1, \infty \}$ に固定することができる。これは $\cp^1$ の $(n+1)$ 個の異なる点のうち3点は $GL(2, \C)$ 不変性により固定されることからも分かる。
前回のエントリーの応用として $Gr(2, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数の系統的な導出を以下に行う。まず、次のような形の多価関数から始めよう。
\[
\Phi = 1^{\al_0} \cdot t^{\al_1} ( 1 -t)^{\al_2}
(1 - z_3 t)^{\al_3} \cdots ( 1 - z_{n} t )^{\al_n} \, = \, \prod_{j=1}^{n} l_j (t)^{\al_j}
\tag{2-3}
\]
ここで、
\[
l_0(t) = 1 \, , ~ l_1(t) = t \, , ~ l_2 (t) = 1 -t
\, , ~ l_j (t) = 1 - z_{j} t ~~ (3 \le j \le n)
\tag{2-4}
\]
である。(1-5), (1-6) と同様に、指数は非整数条件
\[
\al_j \not\in \Z ~~ (0 \le j \le n)\, ,~~~ \sum_{j=0}^{n} \al_j = -2
\tag{2-5}
\]
に従う。以前考えたように、この非整数条件は (2-44)-(2-46)、つまり $F(Z)$ が $F(Z) = \int_\Del \Phi dt$ と表される場合に課される。多価関数 $\Phi$ が定義される空間は
\[
X = \cp^1 - \{ 0 ,1, 1/ z_{3} , \cdots , 1/ z_{n} , \infty \}
\tag{2-6}
\]
で与えられる。$\Phi$ から $X$ のランク1局所系 ${\cal L}$ とその双対局所系 ${\cal L}^{\vee}$ が決まる。よって、(1-50) を用いると、コホモロジー群 $H^1 ( X , {\cal L})$ の基底は
\[
d \log \frac{l_{j+1}}{l_j} ~~~~~~ (0 \le j \le n-1)
\tag{2-7}
\]
で与えられる。いまの場合、ホモロジー群 $H_1 ( X , {\cal L}^{\vee} )$ の基底は分岐点を結ぶ経路の集合で指定される。例えば、そのような基底として
\[
\Del_{\infty 0} \, , \,
\Del_{01} \, , \, \Del_{1\frac{1}{z_3}} \, , \, \Del_{\frac{1}{z_3}\frac{1}{z_4} }
\, , \, \cdots \, , \, \Del_{\frac{1}{z_{n-1}}\frac{1}{z_{n}} }
\tag{2-8}
\]
を選ぶことができる。ここで、$\Del_{pq}$ は分岐点 $p$ と $q$ を結ぶ $\cp^1$ 上の経路を示す。まとめると、(2-3)式の $\Phi$ に付随するホモロジー群の要素 $\Del \in H_1 ( X , {\cal L}^{\vee} )$ に対して、$Gr ( 2, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数の集合
\[
f_j ( Z ) \, = \, \int_\Del \Phi \, d \log \frac{l_{j+1}}{l_j}
\tag{2-9}
\]
を定義することができる。ただし、$0 \le j \le n-1$ である。1変数だけの最も簡単な場合は $n=3$ で与えられ、これはガウスの超幾何関数に相当する。次のエントリーではこの場合について考察する。
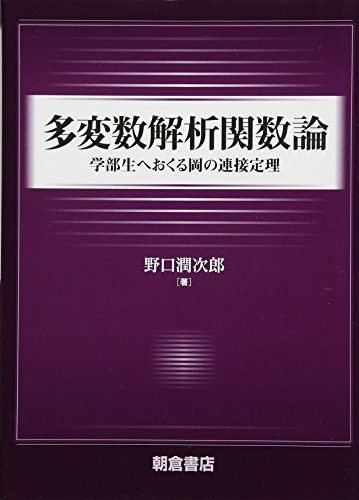

0 件のコメント:
コメントを投稿