私のようなフリーの研究者でも論文を発表していると、所謂ハゲタカジャーナルから雑誌に投稿しないかとか本を書かないかとかの怪しいお誘いがあるのですが、それらは全て迷惑メールとして選別されています。ところが先日迷惑フィルターに掛からない勧誘があったのでおかしいなと思って調べてみると今年の夏に日本とインドの2国間交流事業として共同研究計画を図りませんかというお誘いがあったインド人の数学者からのものでした。その際、私は国の定める研究機関に所属していないので資格がないと丁寧にお断りしたのですが、今回は特殊関数と微分方程式の進展についての本を編集するので1章寄稿してくれとの話でした。分野が違うのでなぜ私に話しが来るのか不思議でしたが、以前に書いた論文でグラスマン多様体上の超幾何関数についてレビューしたのでそのあたりのことをまとめればすぐに書けるはずだと考え快諾しました。この論文はグラスマン多様体上の関数の積分として散乱振幅をとらえるという最近話題になった研究を理解することが動機でしたが、そのためにはまずグラスマン多様体上の関数、特に以前から気になっていたがよく分かっていなかったグラスマン多様体上の超幾何関数
について勉強する必要があったのでまとめのノートを作成しました。この超幾何関数は青本の一般化された超幾何関数と呼ばれています。このときとても参考になった教科書が原岡先生の
でした。だいぶ前(2009年頃)に目黒区立の緑ヶ丘図書館で手に取ってとても興味深かったのですぐに購入しました。この本がなければ上記の青本・喜多の教科書は読み込めなかったと思います。直接面識はありませんが、原岡先生ありがとうございました!グラスマン多様体上の超幾何関数をある特殊なケースに還元したものが昔からよく知られているガウスの超幾何関数に相当するので、この場合について自分なりに手を動かして計算してみました。具体的には、通常は2階微分方程式として表されるガウスの超幾何微分方程式を1階微分方程式として書き換えると、それらの微分方程式にこれまでは明らかでなかった$SL(2, \C)$ 対称性があることが分かりました。このことは複素射影空間$\cp^1$上の正則な(多価)関数が広域共形対称性を持つことから自然なことなのですが、個人的には一般化された超幾何関数の理解に必要な(ツイスト)コホモロジーの概念を使ってこのことを導けたことはとても楽しい発見でした。
ただ、これだけでは物理の論文にならないので、以前の論文では共形場理論の$KZ$方程式の解の積分表示やグルーオンの散乱振幅の積分表示との関係性を示したりしてとても長くなってしましました。今回は純粋に特殊関数や微分方程式の進展に興味がある読者が対象なので、物理的なことは一切省いて上記の発見に至るまでをまとめてみました。興味ある人はこちらを参照してください。
折角なのでこちらのブログでもメインとなる部分を日本語で紹介します。数式や節の振り番号は分かり易いように変更しています。超幾何関数や微分方程式を習ったことのある(あるいは習いたい)学生さんや社会人の方なら読めると思うので挑戦してみてください。微分形式やホモロジー・コホモロジーについて知らない方は和達先生の教科書
などを参考にしてください。それでは少し長くなりますが、入門部分を翻訳します。
$Z$ を $(k+1) \times (n+1)$ 行列
\[
Z = \left(
\begin{array}{ccccc}
z_{00} & z_{01} & z_{02} & \cdots & z_{0n} \\
z_{10} & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
z_{k0} & z_{k1} & z_{k2} & \cdots & z_{kn} \\
\end{array}
\right)
\tag{1-1}
\]
とする。ただし、$k < n$ であり行列要素は複素数 $z_{ij} \in \C$ ($0 \le i \le k \, ;~ 0 \le j \le n $) とする。$Z$の関数 $F(Z)$ がグラスマン多様体 $Gr (k+1, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数と定義されるのは、$F(Z)$ が以下の関係式を満たすときである。
青本の一般化された超幾何関数 [1] の本質は、ツイスト de Rham コホモロジーを用いて、$F(Z)$ が次のように積分表示されるという点にある。
\[
F ( Z ) \, = \, \int_\Delta \Phi \om
\tag{1-7}
\]
\Phi &=& \prod_{j = 0}^{n} l_j (\tau )^{\al_j}
\tag{1-8} \\
l_j (\tau ) &=& \tau_0 z_{0j} + \tau_1 z_{1j}
+ \cdots + \tau_k z_{k j} ~~~~ ( 0 \le j \le n)
\tag{1-9} \\
\om &=& \sum_{i = 0}^{k} ( -1 )^i \tau_i
d \tau_0 \wedge d \tau_1 \wedge \cdots \wedge
d \tau_{i-1} \wedge d \tau_{i + 1} \wedge \cdots \wedge d \tau_k
\tag{1-10}
\end{eqnarray}
$\Delta$ についてさらに考察する前に、積分 (1-7) を計算するに当たり $\om$ がもつ多義性(あいまいさ)に注目しよう。$\al$ を $X$ で定義された任意の$(k -1)$-形式だとすると、完全$k$-形式 $d( \Phi \al )$ の積分はゼロとなる。
\[
0 \, = \, \int_\Delta d ( \Phi \al ) \, = \,
\int_\Delta \Phi \left(
d \al + \frac{d \Phi}{\Phi} \wedge \al
\right) \, = \, \int_\Delta \Phi \nabla \al
\tag{1-13}
\]
ここで、$\nabla$ は共変(外)微分
\[
\nabla \, = \, d + d \log \Phi \wedge \, = \,
d + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{ d l_j}{l_j} \wedge
\tag{1-14}
\]
このコホモロジー類を調べるために、微分方程式
コホモロジー群 $H^k ( X , {\cal L} )$ を定義したので次にその双対、つまり$k$次ホモロジー群 $H_k ( X , {\cal L}^{\vee})$ (あるいはツイスト・ホモロジー群)を定義しよう。ここで ${\cal L}^{\vee}$ は $\Phi$ で与えられるランク1の双対局所系である。${\cal L}^{\vee}$ に対応する微分方程式は
\[
\nabla^{\vee} g \, = \, d g - \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{d l_j}{l_j}
g \, =\, 0
\tag{1-18}
\]
と書ける。この一般解が $\Phi$ で与えられることは簡単にチェックできる。
\[
g \, = \, \la \, \prod_{j = 0}^{n} l_{j} (\tau )^{ \al_j}
\, = \, \la \Phi ~~~~~~
( \la \in \C^{\times} )
\tag{1-19}
\]
以前と同様に $H_k ( X , {\cal L}^{\vee})$ の要素は同値類を与え、ホモロジー類と呼ばれる。
以下では積分経路 $\Del$ が同値類をなし、それがこのホモロジー類と一致することを見る。ストークスの定理より (1-13)式は
$\cp^k$ 上の斉次座標 $\tau = ( \tau_0 , \tau_1 , \cdots , \tau_k )$ を用いて、$\C^{k}$ 上の座標を
について勉強する必要があったのでまとめのノートを作成しました。この超幾何関数は青本の一般化された超幾何関数と呼ばれています。このときとても参考になった教科書が原岡先生の
でした。だいぶ前(2009年頃)に目黒区立の緑ヶ丘図書館で手に取ってとても興味深かったのですぐに購入しました。この本がなければ上記の青本・喜多の教科書は読み込めなかったと思います。直接面識はありませんが、原岡先生ありがとうございました!グラスマン多様体上の超幾何関数をある特殊なケースに還元したものが昔からよく知られているガウスの超幾何関数に相当するので、この場合について自分なりに手を動かして計算してみました。具体的には、通常は2階微分方程式として表されるガウスの超幾何微分方程式を1階微分方程式として書き換えると、それらの微分方程式にこれまでは明らかでなかった$SL(2, \C)$ 対称性があることが分かりました。このことは複素射影空間$\cp^1$上の正則な(多価)関数が広域共形対称性を持つことから自然なことなのですが、個人的には一般化された超幾何関数の理解に必要な(ツイスト)コホモロジーの概念を使ってこのことを導けたことはとても楽しい発見でした。
ただ、これだけでは物理の論文にならないので、以前の論文では共形場理論の$KZ$方程式の解の積分表示やグルーオンの散乱振幅の積分表示との関係性を示したりしてとても長くなってしましました。今回は純粋に特殊関数や微分方程式の進展に興味がある読者が対象なので、物理的なことは一切省いて上記の発見に至るまでをまとめてみました。興味ある人はこちらを参照してください。
折角なのでこちらのブログでもメインとなる部分を日本語で紹介します。数式や節の振り番号は分かり易いように変更しています。超幾何関数や微分方程式を習ったことのある(あるいは習いたい)学生さんや社会人の方なら読めると思うので挑戦してみてください。微分形式やホモロジー・コホモロジーについて知らない方は和達先生の教科書
などを参考にしてください。それでは少し長くなりますが、入門部分を翻訳します。
1. 青本流・グラスマン多様体上の超幾何関数 入門
1.1 定義
$Z$ を $(k+1) \times (n+1)$ 行列
\[
Z = \left(
\begin{array}{ccccc}
z_{00} & z_{01} & z_{02} & \cdots & z_{0n} \\
z_{10} & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
z_{k0} & z_{k1} & z_{k2} & \cdots & z_{kn} \\
\end{array}
\right)
\tag{1-1}
\]
とする。ただし、$k < n$ であり行列要素は複素数 $z_{ij} \in \C$ ($0 \le i \le k \, ;~ 0 \le j \le n $) とする。$Z$の関数 $F(Z)$ がグラスマン多様体 $Gr (k+1, n+1)$ 上の一般化された超幾何関数と定義されるのは、$F(Z)$ が以下の関係式を満たすときである。
\begin{eqnarray}
\sum_{j = 0}^{n} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{pj}} &=& - \del_{ip} F
~~~ ( 0 \le i, p \le k )
\tag{1-2} \\
\sum_{i = 0}^{k} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{ij}} &=& \al_{j} F
~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-3} \\
\frac{\d^2 F}{\d z_{ip}\d z_{jq}} &=& \frac{\d^2 F}{\d z_{iq}\d z_{jp}}
~~~ ( 0 \le i, j \le k \, ; ~ 0 \le p, q \le n )
\tag{1-4}
\end{eqnarray}
\sum_{j = 0}^{n} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{pj}} &=& - \del_{ip} F
~~~ ( 0 \le i, p \le k )
\tag{1-2} \\
\sum_{i = 0}^{k} z_{ij} \frac{\d F}{\d z_{ij}} &=& \al_{j} F
~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-3} \\
\frac{\d^2 F}{\d z_{ip}\d z_{jq}} &=& \frac{\d^2 F}{\d z_{iq}\d z_{jp}}
~~~ ( 0 \le i, j \le k \, ; ~ 0 \le p, q \le n )
\tag{1-4}
\end{eqnarray}
ただし、$\al_j$ は次の非整数条件をみたす。
\begin{eqnarray}
\al_j & \not\in & \Z ~~~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-5} \\
\sum_{j = 0}^{n} \al_j & =& - (k + 1)
\tag{1-6}
\end{eqnarray}
\al_j & \not\in & \Z ~~~~~ ( 0 \le j \le n )
\tag{1-5} \\
\sum_{j = 0}^{n} \al_j & =& - (k + 1)
\tag{1-6}
\end{eqnarray}
1.2 $F(Z)$ の積分表示とツイスト・コホモロジー
青本の一般化された超幾何関数 [1] の本質は、ツイスト de Rham コホモロジーを用いて、$F(Z)$ が次のように積分表示されるという点にある。
F ( Z ) \, = \, \int_\Delta \Phi \om
\tag{1-7}
\]
(ツイスト de Rham コホモロジーは通常の de Rham コホモロジーに下記 (1-8) 式のような多価関数を組み込んだものである。これについて数学的な厳密性については [1] の第2章を参照されたい。)上式で $\Phi$, $\om$ は
\begin{eqnarray}\Phi &=& \prod_{j = 0}^{n} l_j (\tau )^{\al_j}
\tag{1-8} \\
l_j (\tau ) &=& \tau_0 z_{0j} + \tau_1 z_{1j}
+ \cdots + \tau_k z_{k j} ~~~~ ( 0 \le j \le n)
\tag{1-9} \\
\om &=& \sum_{i = 0}^{k} ( -1 )^i \tau_i
d \tau_0 \wedge d \tau_1 \wedge \cdots \wedge
d \tau_{i-1} \wedge d \tau_{i + 1} \wedge \cdots \wedge d \tau_k
\tag{1-10}
\end{eqnarray}
で与えられる。複素変数 $\tau = ( \tau_0 , \tau_1 , \cdots , \tau_k )$ は複素射影空間 $\cp^k$、つまり $\C^{k+1 } - \{ 0, 0, \cdots , 0 \}$、の斉次座標である。よって、多価関数 $\Phi$ は空間
\[
X \, = \, \cp^{k} - \bigcup_{j = 0}^{n} {\cal H}_j
\tag{1-11}
\]
で定義される。ただし、
\[
{\cal H}_j \, = \, \{ \tau \in \cp^k \, ; ~ l_j (\tau ) = 0 \}
\tag{1-12}
\]
である。
\[
X \, = \, \cp^{k} - \bigcup_{j = 0}^{n} {\cal H}_j
\tag{1-11}
\]
で定義される。ただし、
\[
{\cal H}_j \, = \, \{ \tau \in \cp^k \, ; ~ l_j (\tau ) = 0 \}
\tag{1-12}
\]
である。
つぎに、積分経路 $\Delta$ の意味について考えよう。被積分関数は多価の$k$-形式なので、$\Delta$ を $X$ 上の$k$-チェインと単純に選ぶだけでは不十分である。$\Delta$ を選択すると同時に、$\Delta$ 上の $\Phi$ の分岐点を暗に指定する必要がある。そうでなければ積分を正しく定義することはできない。以下では、これらの非明示的な条件を仮定するものとする。
$\Delta$ についてさらに考察する前に、積分 (1-7) を計算するに当たり $\om$ がもつ多義性(あいまいさ)に注目しよう。$\al$ を $X$ で定義された任意の$(k -1)$-形式だとすると、完全$k$-形式 $d( \Phi \al )$ の積分はゼロとなる。
\[
0 \, = \, \int_\Delta d ( \Phi \al ) \, = \,
\int_\Delta \Phi \left(
d \al + \frac{d \Phi}{\Phi} \wedge \al
\right) \, = \, \int_\Delta \Phi \nabla \al
\tag{1-13}
\]
ここで、$\nabla$ は共変(外)微分
\[
\nabla \, = \, d + d \log \Phi \wedge \, = \,
d + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{ d l_j}{l_j} \wedge
\tag{1-14}
\]
と解釈できる。これは、積分 (1-7) の定義において $\om^\prime = \om + \nabla \al$ と $\om$ は同じであることを意味する。つまり、$\om$ と $\om^\prime$ は同値類を成す。($\om \sim \om^\prime$)この同値類はコホモロジー類と呼ばれる。
このコホモロジー類を調べるために、微分方程式
\[
\nabla f \, = \, d f + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{d l_j}{l_j} f \, =\, 0
\tag{1-15}
\]
\nabla f \, = \, d f + \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{d l_j}{l_j} f \, =\, 0
\tag{1-15}
\]
を考えよう。この一般解は局所的に
\[
f \, = \, \la \, \prod_{j = 0}^{n} l_{j} (\tau )^{- \al_j} ~~~~~~
( \la \in \C^{\times} )
\tag{1-16}
\]
と求まる。したがって、これらの局所解は基本的に $1 / \Phi$ で与えられる。ここで局所性の概念は重要である。というのも、たとえ $1 / \Phi$ が多価関数であっても局所的なパッチ(領域)においてこれは一価関数とみなせるからである。これらの解の解析接続は、$X$ 上の閉経路のホモトピー基本群をなす。(より正確には、$X$ でなく $1/X$ 上であるが、(1-8)式の非整数指数 $\al_j$ の符号を変えれば$1/X$ は $X$ とみなすことができる。)この基本群の表現のことをモノドロミー表現と呼ぶ。モノドロミー表現は微分方程式 (1-15) の局所系を決定する。この意味で一般解 $f$ あるいは $1 / \Phi$ はランク1の局所系を与える。(ここで「ランク1」とは局所解 (1-16) において、$l_j ( \tau )$ の各因子が $\tau$ の要素に対して1次のオーダーであることを示す。)
このランク1局所系を ${\cal L}$ で表そう。すると上述のコホモロジー類は ${\cal L}$ 上の $X$ における$k$次のコホモロジー群の要素として定義される。つまり、
\[
[ \om ] \in H^k ( X , {\cal L} )
\tag{1-17}
\]
となる。このコホモロジー群 $H^k ( X , {\cal L} )$ はツイスト・コホモロジー群とも呼ばれる。
f \, = \, \la \, \prod_{j = 0}^{n} l_{j} (\tau )^{- \al_j} ~~~~~~
( \la \in \C^{\times} )
\tag{1-16}
\]
と求まる。したがって、これらの局所解は基本的に $1 / \Phi$ で与えられる。ここで局所性の概念は重要である。というのも、たとえ $1 / \Phi$ が多価関数であっても局所的なパッチ(領域)においてこれは一価関数とみなせるからである。これらの解の解析接続は、$X$ 上の閉経路のホモトピー基本群をなす。(より正確には、$X$ でなく $1/X$ 上であるが、(1-8)式の非整数指数 $\al_j$ の符号を変えれば$1/X$ は $X$ とみなすことができる。)この基本群の表現のことをモノドロミー表現と呼ぶ。モノドロミー表現は微分方程式 (1-15) の局所系を決定する。この意味で一般解 $f$ あるいは $1 / \Phi$ はランク1の局所系を与える。(ここで「ランク1」とは局所解 (1-16) において、$l_j ( \tau )$ の各因子が $\tau$ の要素に対して1次のオーダーであることを示す。)
このランク1局所系を ${\cal L}$ で表そう。すると上述のコホモロジー類は ${\cal L}$ 上の $X$ における$k$次のコホモロジー群の要素として定義される。つまり、
\[
[ \om ] \in H^k ( X , {\cal L} )
\tag{1-17}
\]
となる。このコホモロジー群 $H^k ( X , {\cal L} )$ はツイスト・コホモロジー群とも呼ばれる。
1.3 ツイスト・ホモロジーとツイスト・サイクル
コホモロジー群 $H^k ( X , {\cal L} )$ を定義したので次にその双対、つまり$k$次ホモロジー群 $H_k ( X , {\cal L}^{\vee})$ (あるいはツイスト・ホモロジー群)を定義しよう。ここで ${\cal L}^{\vee}$ は $\Phi$ で与えられるランク1の双対局所系である。${\cal L}^{\vee}$ に対応する微分方程式は
\[
\nabla^{\vee} g \, = \, d g - \sum_{j = 0}^{n} \al_j \frac{d l_j}{l_j}
g \, =\, 0
\tag{1-18}
\]
と書ける。この一般解が $\Phi$ で与えられることは簡単にチェックできる。
\[
g \, = \, \la \, \prod_{j = 0}^{n} l_{j} (\tau )^{ \al_j}
\, = \, \la \Phi ~~~~~~
( \la \in \C^{\times} )
\tag{1-19}
\]
以前と同様に $H_k ( X , {\cal L}^{\vee})$ の要素は同値類を与え、ホモロジー類と呼ばれる。
以下では積分経路 $\Del$ が同値類をなし、それがこのホモロジー類と一致することを見る。ストークスの定理より (1-13)式は
\[
0 \, = \, \int_\Delta \Phi \nabla \al \, = \, \int_{\d \Delta} \Phi \al
\tag{1-20}
\]
と表せる。ここで $\al$ は以前と同じく任意の $(k -1 )$-形式である。境界演算子 $\d$ は基本的に $\Phi$(とその分岐点の情報)から決まる。${\cal L}^{\vee}$ 上の $X$ における $p$次元チェイン群を $C_p ( X , {\cal L}^{\vee})$ であらわすと、境界演算子は $\d \, : \, C_p ( X , {\cal L}^{\vee}) \longrightarrow
C_{p-1} ( X , {\cal L}^{\vee})$ と表せる。関係式 (1-20) が任意の $\al$ で成り立つので、$k$-チェイン $\Del$ は $\d$ の作用でゼロとなる。すなわち、
\[
\d \Delta \, = \, 0
\tag{1-21}
\]
このような $k$-チェイン $\Del$ は一般に$k$-サイクルと呼ばれる。今の枠組みにおいて、これはツイスト・サイクルとも呼ばれる。境界演算子は条件 $\d^2 = 0$ をみたすので、$k$-サイクルはそれ自体に余剰性が含まれる。つまり、$\Del^\prime = \Del + \d C_{(+1)}$ も同様に $k$-サイクルとなる。ただし、$C_{(+1)}$ は任意の $( k + 1 )$-チェイン、あるいは $C_{k+1} ( X , {\cal L}^{\vee})$ の要素である。従って、$\Del$ と $\Del^\prime$ は同値類を形成し($\Del \sim \Del^\prime$)、これはまさに $H_k ( X , {\cal L}^{\vee} )$ で定義されるホモロジー類である。すなわち、
\[
[ \Delta ] \in H_k ( X , {\cal L}^{\vee} )
\tag{1-22}
\]
となる。
まとめると、一般化された超幾何関数 (1-7) は次の双線形形式で決定される。
\begin{eqnarray}
H_k ( X , {\cal L}^{\vee} ) \times H^k ( X , {\cal L} )
& \longrightarrow & \C
\tag{1-23} \\
\left( [ \Delta ], [ \om ] \right) & \longrightarrow &
\int_{\Del} \Phi \om
\tag{1-24}
\end{eqnarray}
0 \, = \, \int_\Delta \Phi \nabla \al \, = \, \int_{\d \Delta} \Phi \al
\tag{1-20}
\]
と表せる。ここで $\al$ は以前と同じく任意の $(k -1 )$-形式である。境界演算子 $\d$ は基本的に $\Phi$(とその分岐点の情報)から決まる。${\cal L}^{\vee}$ 上の $X$ における $p$次元チェイン群を $C_p ( X , {\cal L}^{\vee})$ であらわすと、境界演算子は $\d \, : \, C_p ( X , {\cal L}^{\vee}) \longrightarrow
C_{p-1} ( X , {\cal L}^{\vee})$ と表せる。関係式 (1-20) が任意の $\al$ で成り立つので、$k$-チェイン $\Del$ は $\d$ の作用でゼロとなる。すなわち、
\[
\d \Delta \, = \, 0
\tag{1-21}
\]
このような $k$-チェイン $\Del$ は一般に$k$-サイクルと呼ばれる。今の枠組みにおいて、これはツイスト・サイクルとも呼ばれる。境界演算子は条件 $\d^2 = 0$ をみたすので、$k$-サイクルはそれ自体に余剰性が含まれる。つまり、$\Del^\prime = \Del + \d C_{(+1)}$ も同様に $k$-サイクルとなる。ただし、$C_{(+1)}$ は任意の $( k + 1 )$-チェイン、あるいは $C_{k+1} ( X , {\cal L}^{\vee})$ の要素である。従って、$\Del$ と $\Del^\prime$ は同値類を形成し($\Del \sim \Del^\prime$)、これはまさに $H_k ( X , {\cal L}^{\vee} )$ で定義されるホモロジー類である。すなわち、
\[
[ \Delta ] \in H_k ( X , {\cal L}^{\vee} )
\tag{1-22}
\]
となる。
まとめると、一般化された超幾何関数 (1-7) は次の双線形形式で決定される。
\begin{eqnarray}
H_k ( X , {\cal L}^{\vee} ) \times H^k ( X , {\cal L} )
& \longrightarrow & \C
\tag{1-23} \\
\left( [ \Delta ], [ \om ] \right) & \longrightarrow &
\int_{\Del} \Phi \om
\tag{1-24}
\end{eqnarray}
1.4 $F(Z)$ のみたす微分方程式
(1-12)式での条件式 $l_j (\tau ) = 0$ によって$(k+1)$次元空間での超平面 (hyperplane) が定義される。超平面の配置の余剰性を避けるために、超平面は非縮退であると仮定する。別の言葉でいうと、一般の位置にある超平面 (hyperplanes in general position) を考えることにする。この仮定は、$(k+1) \times (n+1)$行列 $Z$ の任意の $(k+1)$ 次元小行列式がゼロにならないことを要請することで実現できる。そこで、(1-11) で定義された $X$ を
\[
X = \{
Z \in Mat_{k+1 , n+1} ( \C ) | \mbox{ $Z$ の$(k+1)$次元小行列式はすべてゼロでない}
\}
\tag{1-25}
\]
と再定義しよう。以下では、行列 $Z$ はこの条件を満たすものとする。複素射影空間 $\cp^k$ 上の $n+1$個の超平面の配置はこの行列 $Z$ から決まる。
超平面の概念とは別に、行列 $Z$ から $\cp^k$ 上の異なる $n+1$ 個の点が求まると解釈することもできる。$\cp^k$ の斉次座標は $\C^{k+1} - \{0, 0, \cdots, 0 \}$ で与えられるので、$Z$ の $n+1$ 個の列ベクトルそれぞれを $\cp^k$ 上の「点」とみなすことができる。例えば、$j$-番目の列ベクトルは $\cp^k$ の $j$-番目の斉次座標を表していると考えることができる $(j = 0,1, \cdots , n)$ 。
定義から$\cp^k$ の斉次座標はスケール変換のもとで不変であるが、このスケール変換は対角行列 $H_{n+1} = \{ \diag (h_0 , h_1 , \cdots h_n ) | h_j \in \C^\times \}$ を右から $Z$ に作用させることで実現できる。一方、斉次座標の一般線形変換は $GL(k+1, \C)$ を左から作用させることで実現できる。よって、これらの変換は
\begin{eqnarray}
{\mbox 線形変換:}&~& Z \rightarrow Z^\prime = g Z
\tag{1-26} \\
{\mbox スケール変換:}&~& Z \rightarrow Z^\prime = Z h
\tag{1-27}
\end{eqnarray}
で与えられる。ただし、$g \in GL(k+1, \C)$、$h \in H_{n+1}$ である。これらの変換のもとで (1-7) の積分 $F(Z)$ は
\begin{eqnarray}
F (g Z ) &=& (\det g)^{-1} F(Z)
\tag{1-28}\\
F ( Z h ) &=& F (Z) \prod_{j = 0}^{n} h_{j}^{\al_j}
\tag{1-29}
\end{eqnarray}
と変換する。
次にこれらの関係式が、グラスマン多様体上に一般化された超幾何関数の定義式 (1-2), (1-3) を導くことを簡単に示そう。${\bf 1}_n$ を$n$次元の単位行列 ${\bf 1}_n
= \diag ( 1,1, \cdots ,1)$、$E_{ij}^{(n)}$ を $(i,j)$-要素だけが1で残りがゼロの $n \times n$ 行列とする。このとき $g$ として
\[
g = {\bf 1}_{k+1} + \ep E^{(k+1)}_{pi}
\tag{1-30}
\]
という特定の形のものを考える。ただし、$\ep$ はパラメータ。このとき $gZ$ は $Z$ の $p$-番目の行が $(z_{p0} + \ep z_{i0}, z_{p1} + \ep z_{i1}, \cdots,
z_{pn} + \ep z_{in})$ で置き換えられたものとなる。よって、$F(gZ)$ を $\ep$ で微分すると
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (gZ) \, = \, \sum_{j=0}^{n} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{pj}} F(gZ)
\tag{1-31}
\]
なる。一方、
\[
\det g = \left\{
\begin{array}{l}
1 ~~~ (i \ne p) \\
\ep ~~~ (i = p ) \\
\end{array}
\right.
\tag{1-32}
\]
\frac{\d}{\d \ep} F (gZ) = \left\{
\begin{array}{l}
~~~~ 0 ~~~~~~~~~~~~~ (i \ne p) \\
- \frac{1}{\ep^2} F(Z) ~~~ (i = p ) \\
\end{array}
\right.
\tag{1-33}
\]
を得る。よって、微分を $i \ne p$ と $i = p$ についてそれぞれ $\ep = 0$ と $\ep = 1$ で評価すると、(1-28) は確かに微分方程式 (1-2) を導くことがわかる。
同様に、$h$ を
\[
h = \diag( h_0 , \cdots , h_{j-1} , (1+ \ep )h_j , h_{j+1} , \cdots , h_n )
\tag{1-34}
\]
$(0 \le j \le n)$ とパラメータ表示すると、$Zh$ の $\ep$-依存性は $j$-番目の列ベクトル $\left( z_{0j}( 1 +\ep )h_j , z_{1j} ( 1 +\ep )h_j, \cdots , z_{kj} ( 1 +\ep )h_j \right)^{T}$ だけに現れる。$\ep$ について $F(Zh)$ の微分をとると
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (Zh) \, = \, \sum_{i=0}^{k} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{ij}} F(Zh) \, = \, \sum_{i=0}^{k} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{ij}} F(Z)(1+ \ep )^{\al_j} \prod_{ l = 0}^{n} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-35}
\]
となる。ここで、最後の等号で関係式(1-29):
\[
F (Zh ) \, = \, F(Z) (1+ \ep )^{\al_j} \prod_{ l = 0}^{n} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-36}
\]
を用いた。これより同じ微分は
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (Zh) \, = \, \al_j F(Z) (1+ \ep )^{\al_j - 1}
\prod_{ l = 0}^{k} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-37}
\]
と計算できる。したがって、$\ep = 0$ とおくと方程式 (1-3) を導出できる。
$F(Z)$についての残りの関係式 (1-4) は $\Phi$ の定義から分かる。(1-8) と (1-9) から
$\Phi$ が
\[
\frac{\d \Phi}{\d z_{ip} } \, = \, \frac{ \al_i \tau_p}{l_i (\tau) } \Phi
\tag{1-38}
\]
を満たすことがわかる。この関係式から
\[
\frac{\d^2 \Phi}{\d z_{ip} \d z_{jq} } \, = \,
\frac{ \al_i \al_j \tau_p \tau_q}{l_i (\tau) l_j (\tau) } \Phi
\, = \, \frac{\d^2 \Phi}{\d z_{iq} \d z_{jp} }
\tag{1-39}
\]
となり、これより直ちに方程式 (1-4) が得られる。
以上から、(1-7) の積分 $F(Z)$ が確かに $Gr ( k+1 , n+1 )$ 上の一般化された超幾何関数の定義式 (2-2)-(2-4) を満たすことが分かった。グラスマン多様体 $Gr ( k+1 , n+1 )$ は $(n+1)$次元の複素ベクトル空間 $\C^{n+1}$ における $(k+1)$次元の線形部分空間として定義される。つまり、
\[
Gr ( k+1 ,n+1 ) \, = \, \widetilde{Z} / GL (k+1 ,\C )
\tag{1-40}
\]
と定義される。ただし、$\widetilde{Z}$ は $rank \widetilde{Z} = k+1$ となる $(k+1)\times (n+1)$ 複素行列を表す。一般に行列 $M$ がゼロでない $r$次元の小行列式を持つ場合、$M$ のランクはそのような $r$ のうちで最大のもので定義される。したがって、$\widetilde{Z}$ は (1-25) で定義された $Z$ とは正確には一致しない。 $\widetilde{Z}$ はより条件が緩められた行列と言える。というのも、$\widetilde{Z}$ では $(k+1)$次元の小行列式のうちにゼロとなるものがあっても良いからである。つまり、$Z \subseteq \widetilde{Z}$ となる。この意味で $F(Z)$ は慣習的に $Gr (k+1,n+1)$ 上の一般化された超幾何関数と呼ばれる。
\[
X = \{
Z \in Mat_{k+1 , n+1} ( \C ) | \mbox{ $Z$ の$(k+1)$次元小行列式はすべてゼロでない}
\}
\tag{1-25}
\]
と再定義しよう。以下では、行列 $Z$ はこの条件を満たすものとする。複素射影空間 $\cp^k$ 上の $n+1$個の超平面の配置はこの行列 $Z$ から決まる。
超平面の概念とは別に、行列 $Z$ から $\cp^k$ 上の異なる $n+1$ 個の点が求まると解釈することもできる。$\cp^k$ の斉次座標は $\C^{k+1} - \{0, 0, \cdots, 0 \}$ で与えられるので、$Z$ の $n+1$ 個の列ベクトルそれぞれを $\cp^k$ 上の「点」とみなすことができる。例えば、$j$-番目の列ベクトルは $\cp^k$ の $j$-番目の斉次座標を表していると考えることができる $(j = 0,1, \cdots , n)$ 。
定義から$\cp^k$ の斉次座標はスケール変換のもとで不変であるが、このスケール変換は対角行列 $H_{n+1} = \{ \diag (h_0 , h_1 , \cdots h_n ) | h_j \in \C^\times \}$ を右から $Z$ に作用させることで実現できる。一方、斉次座標の一般線形変換は $GL(k+1, \C)$ を左から作用させることで実現できる。よって、これらの変換は
\begin{eqnarray}
{\mbox 線形変換:}&~& Z \rightarrow Z^\prime = g Z
\tag{1-26} \\
{\mbox スケール変換:}&~& Z \rightarrow Z^\prime = Z h
\tag{1-27}
\end{eqnarray}
で与えられる。ただし、$g \in GL(k+1, \C)$、$h \in H_{n+1}$ である。これらの変換のもとで (1-7) の積分 $F(Z)$ は
\begin{eqnarray}
F (g Z ) &=& (\det g)^{-1} F(Z)
\tag{1-28}\\
F ( Z h ) &=& F (Z) \prod_{j = 0}^{n} h_{j}^{\al_j}
\tag{1-29}
\end{eqnarray}
と変換する。
次にこれらの関係式が、グラスマン多様体上に一般化された超幾何関数の定義式 (1-2), (1-3) を導くことを簡単に示そう。${\bf 1}_n$ を$n$次元の単位行列 ${\bf 1}_n
= \diag ( 1,1, \cdots ,1)$、$E_{ij}^{(n)}$ を $(i,j)$-要素だけが1で残りがゼロの $n \times n$ 行列とする。このとき $g$ として
\[
g = {\bf 1}_{k+1} + \ep E^{(k+1)}_{pi}
\tag{1-30}
\]
という特定の形のものを考える。ただし、$\ep$ はパラメータ。このとき $gZ$ は $Z$ の $p$-番目の行が $(z_{p0} + \ep z_{i0}, z_{p1} + \ep z_{i1}, \cdots,
z_{pn} + \ep z_{in})$ で置き換えられたものとなる。よって、$F(gZ)$ を $\ep$ で微分すると
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (gZ) \, = \, \sum_{j=0}^{n} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{pj}} F(gZ)
\tag{1-31}
\]
なる。一方、
\[
\det g = \left\{
\begin{array}{l}
1 ~~~ (i \ne p) \\
\ep ~~~ (i = p ) \\
\end{array}
\right.
\tag{1-32}
\]
と関係式 (1-28) を用いると、
\[\frac{\d}{\d \ep} F (gZ) = \left\{
\begin{array}{l}
~~~~ 0 ~~~~~~~~~~~~~ (i \ne p) \\
- \frac{1}{\ep^2} F(Z) ~~~ (i = p ) \\
\end{array}
\right.
\tag{1-33}
\]
を得る。よって、微分を $i \ne p$ と $i = p$ についてそれぞれ $\ep = 0$ と $\ep = 1$ で評価すると、(1-28) は確かに微分方程式 (1-2) を導くことがわかる。
同様に、$h$ を
\[
h = \diag( h_0 , \cdots , h_{j-1} , (1+ \ep )h_j , h_{j+1} , \cdots , h_n )
\tag{1-34}
\]
$(0 \le j \le n)$ とパラメータ表示すると、$Zh$ の $\ep$-依存性は $j$-番目の列ベクトル $\left( z_{0j}( 1 +\ep )h_j , z_{1j} ( 1 +\ep )h_j, \cdots , z_{kj} ( 1 +\ep )h_j \right)^{T}$ だけに現れる。$\ep$ について $F(Zh)$ の微分をとると
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (Zh) \, = \, \sum_{i=0}^{k} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{ij}} F(Zh) \, = \, \sum_{i=0}^{k} z_{ij}
\frac{\d }{\d z_{ij}} F(Z)(1+ \ep )^{\al_j} \prod_{ l = 0}^{n} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-35}
\]
となる。ここで、最後の等号で関係式(1-29):
\[
F (Zh ) \, = \, F(Z) (1+ \ep )^{\al_j} \prod_{ l = 0}^{n} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-36}
\]
を用いた。これより同じ微分は
\[
\frac{\d}{\d \ep} F (Zh) \, = \, \al_j F(Z) (1+ \ep )^{\al_j - 1}
\prod_{ l = 0}^{k} h_{l}^{\al_l}
\tag{1-37}
\]
と計算できる。したがって、$\ep = 0$ とおくと方程式 (1-3) を導出できる。
$F(Z)$についての残りの関係式 (1-4) は $\Phi$ の定義から分かる。(1-8) と (1-9) から
$\Phi$ が
\[
\frac{\d \Phi}{\d z_{ip} } \, = \, \frac{ \al_i \tau_p}{l_i (\tau) } \Phi
\tag{1-38}
\]
を満たすことがわかる。この関係式から
\[
\frac{\d^2 \Phi}{\d z_{ip} \d z_{jq} } \, = \,
\frac{ \al_i \al_j \tau_p \tau_q}{l_i (\tau) l_j (\tau) } \Phi
\, = \, \frac{\d^2 \Phi}{\d z_{iq} \d z_{jp} }
\tag{1-39}
\]
となり、これより直ちに方程式 (1-4) が得られる。
以上から、(1-7) の積分 $F(Z)$ が確かに $Gr ( k+1 , n+1 )$ 上の一般化された超幾何関数の定義式 (2-2)-(2-4) を満たすことが分かった。グラスマン多様体 $Gr ( k+1 , n+1 )$ は $(n+1)$次元の複素ベクトル空間 $\C^{n+1}$ における $(k+1)$次元の線形部分空間として定義される。つまり、
\[
Gr ( k+1 ,n+1 ) \, = \, \widetilde{Z} / GL (k+1 ,\C )
\tag{1-40}
\]
と定義される。ただし、$\widetilde{Z}$ は $rank \widetilde{Z} = k+1$ となる $(k+1)\times (n+1)$ 複素行列を表す。一般に行列 $M$ がゼロでない $r$次元の小行列式を持つ場合、$M$ のランクはそのような $r$ のうちで最大のもので定義される。したがって、$\widetilde{Z}$ は (1-25) で定義された $Z$ とは正確には一致しない。 $\widetilde{Z}$ はより条件が緩められた行列と言える。というのも、$\widetilde{Z}$ では $(k+1)$次元の小行列式のうちにゼロとなるものがあっても良いからである。つまり、$Z \subseteq \widetilde{Z}$ となる。この意味で $F(Z)$ は慣習的に $Gr (k+1,n+1)$ 上の一般化された超幾何関数と呼ばれる。
1.5 非射影化
$\cp^k$ 上の斉次座標 $\tau = ( \tau_0 , \tau_1 , \cdots , \tau_k )$ を用いて、$\C^{k}$ 上の座標を
\[
t_1 = \frac{\tau_1}{\tau_0} ~, ~ t_1 = \frac{\tau_1}{\tau_0} ~,~
\cdots ~, ~ t_k = \frac{\tau_k}{\tau_0}
\tag{1-41}
\]
とパラメータ表示できる。簡単のため、ここで $(z_{00} , z_{10} , \cdots , z_{n0} )^T$ を $(1, 0, \cdots, 0)^T$ と固定しよう。つまり、
\[
Z = \left(
\begin{array}{ccccc}
1 & z_{01} & z_{02} & \cdots & z_{0n} \\
0 & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & z_{k1} & z_{k2} & \cdots & z_{kn} \\
\end{array}
\right)
\tag{1-42}
\]
とする。すると、$F(Z)$ の被積分関数は
\begin{eqnarray}
\Phi \om & = &
\tau_{0}^{\al_0} \prod_{j = 1}^{n}
\left( \tau_0 z_{0j} + \tau_1 z_{1j} + \cdots + \tau_k z_{kj} \right)^{\al_j} \,
\nonumber \\
&& ~~ \times
\sum_{i = 0}^{k} ( -1 )^i \tau_i
d \tau_0 \wedge d \tau_1 \wedge \cdots \wedge
d \tau_{i-1} \wedge d \tau_{i + 1} \wedge \cdots \wedge d \tau_k
\nonumber \\
&=&
\prod_{j = 1}^{n}
\left( z_{0j} + \frac{\tau_1}{\tau_0} z_{1j} + \cdots + \frac{\tau_k}{\tau_0} z_{kj} \right)^{\al_j}
d \left( \frac{\tau_1}{\tau_0} \right) \wedge d \left( \frac{\tau_2}{\tau_0} \right)
\wedge \cdots \wedge d \left( \frac{\tau_k}{\tau_0} \right)
\nonumber \\
& =& \widetilde{\Phi} \widetilde{\om}
\tag{1-43}
\end{eqnarray}
と表される。ただし、(1-6) を用いた。また、$\widetilde{\Phi}$, $\widetilde{\om}$ は
\begin{eqnarray}
\widetilde{\Phi} &=& \prod_{j=1}^{n} \widetilde{l}_j (t)^{\al_j}
\tag{1-44} \\
\widetilde{l}_j (t) &=& z_{0j} + t_1 z_{1j} + t_2 z_{2j} + \cdots + t_k z_{kj}
~~~~~ ( 1 \le j \le n )
\tag{1-45} \\
\widetilde{\om} &=& dt_1 \wedge dt_2 \wedge \cdots \wedge dt_k
\tag{1-46}
\end{eqnarray}
で定義される。以前同様、指数 $\al_j$ $(j= 1,2,\cdots, n)$ には非整数条件 $\al_j \not\in \Z $ 及び $\al_1 + \al_2 + \cdots + \al_n \not\in \Z$ が課される。このとき多価関数 $\widetilde{\Phi}$ は次の空間で定義される。
\[
\widetilde{X} \, = \, \C^k - \bigcup_{j= 1}^{n} \widetilde{{\cal H}}_j
\tag{1-47}
\]
ただし、
\[
\widetilde{{\cal H}}_j \, = \, \{ t \in \C^k \, ; ~ \widetilde{l}_j (t) = 0 \}
\tag{1-48}
\]
である。これらは (1-11) と (1-12) の非射影化バージョンである。
以前と同様に、$\widetilde{\Phi}$ から $\widetilde{X}$ 上のランク1局所系、双対局所系 $\widetilde{\cal L}$, $\widetilde{\cal L}^{\vee}$ を定義でき、これらより $k$次元のホモロジー群とコホモロジー群 $H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$, $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ を導くことができる。よって、$\widetilde{\Phi} \widetilde{\om}$ の積分は
\[
F(Z) \, = \, \int_{\widetilde{\Del}}\widetilde{\Phi} \widetilde{\om}
\tag{1-49}
\]
と定義できる。ただし、$[ \widetilde{\Del} ] = H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$, $[ \widetilde{\om} ] = H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ である。
コホモロジー群 $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ に関して青本による次の定理がある ([1] 116ページの定理9.6.2から):
1. $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の次元は $\left(
\begin{array}{c}
\!\! n-1 \!\! \\
\!\! k \!\! \\
\end{array}
\right)$ で与えられる。
2. $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の基底として $d \log \widetilde{l}_{j_1} \wedge d \log \widetilde{l}_{j_1} \wedge
\cdots \wedge d \log \widetilde{l}_{j_k}$ を取れる。ただし、$1\le j_1 < j_2 < \cdots < j_k \le n-1$ である。
これに対応して、ホモトピー群 $H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$ も次元 $\left(
\begin{array}{c}
\!\! n-1 \!\! \\
\!\! k \!\! \\
\end{array}
\right)$ をもち、その基底は $\widetilde{\cal H}_j$ を境界にもつ有限領域にとることができる。コホモロジー群 $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の基底については、$\widetilde{l}_j$ を用いてつぎのように選ぶこともできる [2]:
\[
\varphi_{j_1 j_2 \dots j_k} \, = \,
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_1 + 1}}{ \widetilde{l}_{j_1}}
\wedge
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_2 + 1}}{ \widetilde{l}_{j_2}}
\wedge
\cdots
\wedge
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_k + 1}}{ \widetilde{l}_{j_k}}
\tag{1-50}
\]
ただし、$1\le j_1 < j_2 < \cdots < j_k \le n-1$ である。
t_1 = \frac{\tau_1}{\tau_0} ~, ~ t_1 = \frac{\tau_1}{\tau_0} ~,~
\cdots ~, ~ t_k = \frac{\tau_k}{\tau_0}
\tag{1-41}
\]
とパラメータ表示できる。簡単のため、ここで $(z_{00} , z_{10} , \cdots , z_{n0} )^T$ を $(1, 0, \cdots, 0)^T$ と固定しよう。つまり、
\[
Z = \left(
\begin{array}{ccccc}
1 & z_{01} & z_{02} & \cdots & z_{0n} \\
0 & z_{11} & z_{12} & \cdots & z_{1n} \\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
0 & z_{k1} & z_{k2} & \cdots & z_{kn} \\
\end{array}
\right)
\tag{1-42}
\]
とする。すると、$F(Z)$ の被積分関数は
\begin{eqnarray}
\Phi \om & = &
\tau_{0}^{\al_0} \prod_{j = 1}^{n}
\left( \tau_0 z_{0j} + \tau_1 z_{1j} + \cdots + \tau_k z_{kj} \right)^{\al_j} \,
\nonumber \\
&& ~~ \times
\sum_{i = 0}^{k} ( -1 )^i \tau_i
d \tau_0 \wedge d \tau_1 \wedge \cdots \wedge
d \tau_{i-1} \wedge d \tau_{i + 1} \wedge \cdots \wedge d \tau_k
\nonumber \\
&=&
\prod_{j = 1}^{n}
\left( z_{0j} + \frac{\tau_1}{\tau_0} z_{1j} + \cdots + \frac{\tau_k}{\tau_0} z_{kj} \right)^{\al_j}
d \left( \frac{\tau_1}{\tau_0} \right) \wedge d \left( \frac{\tau_2}{\tau_0} \right)
\wedge \cdots \wedge d \left( \frac{\tau_k}{\tau_0} \right)
\nonumber \\
& =& \widetilde{\Phi} \widetilde{\om}
\tag{1-43}
\end{eqnarray}
と表される。ただし、(1-6) を用いた。また、$\widetilde{\Phi}$, $\widetilde{\om}$ は
\begin{eqnarray}
\widetilde{\Phi} &=& \prod_{j=1}^{n} \widetilde{l}_j (t)^{\al_j}
\tag{1-44} \\
\widetilde{l}_j (t) &=& z_{0j} + t_1 z_{1j} + t_2 z_{2j} + \cdots + t_k z_{kj}
~~~~~ ( 1 \le j \le n )
\tag{1-45} \\
\widetilde{\om} &=& dt_1 \wedge dt_2 \wedge \cdots \wedge dt_k
\tag{1-46}
\end{eqnarray}
で定義される。以前同様、指数 $\al_j$ $(j= 1,2,\cdots, n)$ には非整数条件 $\al_j \not\in \Z $ 及び $\al_1 + \al_2 + \cdots + \al_n \not\in \Z$ が課される。このとき多価関数 $\widetilde{\Phi}$ は次の空間で定義される。
\[
\widetilde{X} \, = \, \C^k - \bigcup_{j= 1}^{n} \widetilde{{\cal H}}_j
\tag{1-47}
\]
ただし、
\[
\widetilde{{\cal H}}_j \, = \, \{ t \in \C^k \, ; ~ \widetilde{l}_j (t) = 0 \}
\tag{1-48}
\]
である。これらは (1-11) と (1-12) の非射影化バージョンである。
以前と同様に、$\widetilde{\Phi}$ から $\widetilde{X}$ 上のランク1局所系、双対局所系 $\widetilde{\cal L}$, $\widetilde{\cal L}^{\vee}$ を定義でき、これらより $k$次元のホモロジー群とコホモロジー群 $H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$, $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ を導くことができる。よって、$\widetilde{\Phi} \widetilde{\om}$ の積分は
\[
F(Z) \, = \, \int_{\widetilde{\Del}}\widetilde{\Phi} \widetilde{\om}
\tag{1-49}
\]
と定義できる。ただし、$[ \widetilde{\Del} ] = H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$, $[ \widetilde{\om} ] = H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ である。
コホモロジー群 $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ に関して青本による次の定理がある ([1] 116ページの定理9.6.2から):
1. $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の次元は $\left(
\begin{array}{c}
\!\! n-1 \!\! \\
\!\! k \!\! \\
\end{array}
\right)$ で与えられる。
2. $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の基底として $d \log \widetilde{l}_{j_1} \wedge d \log \widetilde{l}_{j_1} \wedge
\cdots \wedge d \log \widetilde{l}_{j_k}$ を取れる。ただし、$1\le j_1 < j_2 < \cdots < j_k \le n-1$ である。
これに対応して、ホモトピー群 $H_k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L}^{\vee})$ も次元 $\left(
\begin{array}{c}
\!\! n-1 \!\! \\
\!\! k \!\! \\
\end{array}
\right)$ をもち、その基底は $\widetilde{\cal H}_j$ を境界にもつ有限領域にとることができる。コホモロジー群 $H^k ( \widetilde{X}, \widetilde{\cal L})$ の基底については、$\widetilde{l}_j$ を用いてつぎのように選ぶこともできる [2]:
\[
\varphi_{j_1 j_2 \dots j_k} \, = \,
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_1 + 1}}{ \widetilde{l}_{j_1}}
\wedge
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_2 + 1}}{ \widetilde{l}_{j_2}}
\wedge
\cdots
\wedge
d \log \frac{ \widetilde{l}_{j_k + 1}}{ \widetilde{l}_{j_k}}
\tag{1-50}
\]
ただし、$1\le j_1 < j_2 < \cdots < j_k \le n-1$ である。
参考文献
1. 青本和彦, 喜多通武,『超幾何関数論』シュプリンガー・フェアラーク東京, 1994.
2. 原岡喜重, 『超幾何関数』(すうがくの風景)朝倉書店, 2002.
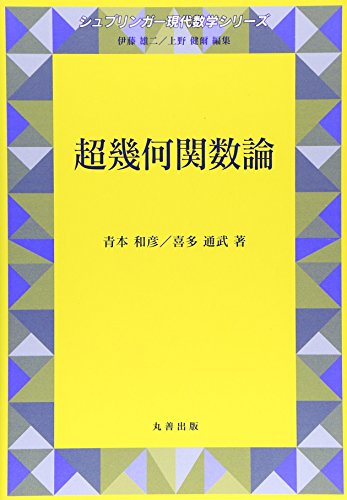


0 件のコメント:
コメントを投稿