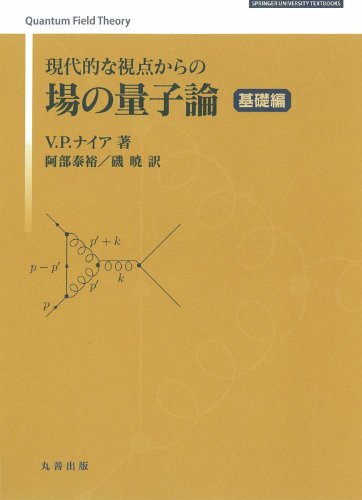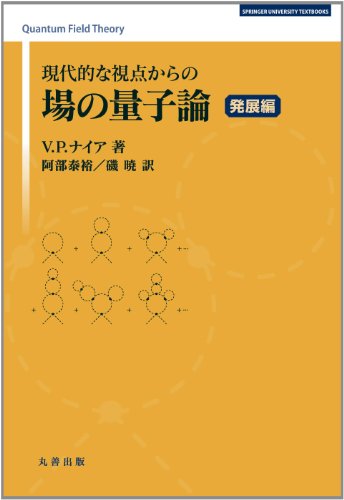以前のノート
note11でQCDの「フレーバーカイラル対称性の破れの階層性」について触れましたが、今回のエントリーではこの点について更に詳しく見て行くことにする。
QCDのフェルミオン部分のラグランジアンは
\[ \L = - \sum_{i = 1}^{N_f} \bar{q}_i \ga \cdot D q_i + \mbox{(質量項)} \tag{1}\]
で与えられる。ただし、$D = \d + A$ であり、$A$ はグルーオンを表す。古典レベルでこのラグランジアンの最大の対称性は $U(N_f)_L \times U(N_f )_R$ となる。これは
\[ \L = - \bar{q}_{Li} \ga \cdot \d q_{Li} - \bar{q}_{Ri} \ga \cdot \d q_{Ri} + \cdots \tag{2} \]
と書き下せば明らかである。実際にはこのフレーバーカイラル対称性は実現されていない。以下ではカイラル対称性が破れる原因を紹介していく。
(1) 電弱相互作用
電弱ゲージ群 $G_W \subset U(N_f)_L \times U(N_f )_R$ によって明示的にカイラル対称性が破れる。この対称性の破れはクォークと $W, Z$ ボソンとの相互作用、クォークとヒッグス場との相互作用を通して起きる。これらの相互作用はQCDラグランジアンの摂動的な補正として扱われ、クォークの質量項だけが残る。これは電弱摂動理論のゼロオーダーであり、そのラグランジアンは
\[ \L = - \bar{q}_i \ga \cdot (\d + A ) q_i - m_i \bar{q}_i q_i \tag{3} \]
で与えられる。このラグランジアンの対称性はとても小さい。全ての軸性対称性は質量項のために自明的に破れる。もし全ての $m_i$ が等しければ $U(N_f )_{L+R}$ 対称性が保たれる。しかし、質量差を考量すると $U(N_f )_{L+R}$ より小さな対称性しか持ちえない。$N_f =3$ の場合、
\[ U(N_f )_{L+R} = U(3)_V \approx SU(3)_V \times U(1) \]
となる。ここで、$SU(3)_V$ は
GellMann-Ne'emanによって提唱されたクォーク模型の $SU(3)$ 群である。$U(1)$ はバリオン数を表す。
(2) 強い相互作用によるカイラル対称性の自発的な破れ
クォークの質量も含めて全ての電弱相互作用項が無視できる場合、古典的な対称性は $U(N_f )_L \times U(N_f )_R$ である。この対称性は強い相互作用の閉じ込め効果により $U(N_f )_{L+R}$ へ自発的に破れる。これは実験的な事実であるが、理論的に証明されたわけではない。これは自発的な破れの効果によるものでオーダーパラメータを使って記述できる。簡単なオーダーパラメータとして複合演算子 $\bar{q}_{Li}q_{Rj}=M_{ij}$ を採用する。
\[ \bra \bar{q}_{Li}q_{Rj} \ket = \bra M_{ij} \ket = c \del_{ij} \tag{4} \]
$U(N_f )_L \times U(N_f )_R$ 変換のもとで $M \rightarrow h^\dagger M g$ となる。ただし、$ h \in U(N_f )_L $, $g \in U(N_f )_R $ である。$\bra M \ket = c {\bf 1}$ のとき $U(N_f )_{L+R}$ は保存される。$\bra M \ket$ が ${\bf 1}$ に比例しない場合($c$-数でない場合)対称性の破れ方は異なる。パリティは自発的に破れない。実際、ヴァッファとウィッテンによりベクトル的な対称性は自発的に破れないことが示されている 。すなわち、自発的な対称性の破れによって $U(N_f )_{L+R}$ より小さな対称性が得られることは無い。
ゴールドストンの定理により自発的な対称性の破れ $U(N_f )_L \times U(N_f )_R \rightarrow U(N_f )_{L+R}$ によってコセット多様体 $\frac{U(N_f )_L \times U(N_f )_R}{U(N_f )_{V}}$ に対応する南部-ゴールドストン粒子が導かれる。これらは標準的な擬スカラーメソン $\pi, K , \eta ,\eta'$ を与える。元となるカイラル対称性 $U(N_f )_L \times U(N_f )_R$ はクォークの質量とその他の電弱相互作用によって自明的に破れるので理論の完全な対称性ではない。そのため、これらの擬スカラーメソンは現実世界では無質量とならない。
(3) 軸性アノマリー
軸性アノマリーについて詳しくは
note07を参照のこと。古典的な対称性は $U(N_f )_L \times U(N_f )_R \rightarrow U(N_f )_{L+R}$ であるが、フレーバー1重項の軸性 $U(1)$ 対称性はアノマリーによって破られる。このアノマリーは
\[ q \rightarrow e^{i \ga_5 \al } q \]
\[ \del_\al \Ga = 2 \al N_f \left[\frac{1}{16 \pi^2} \int F_{\mu\nu}^{a} \widetilde{F}_{\mu\nu}^{a} \right] = 2 \al N_f Q\tag{5} \]
となる。ただし、$Q$ は整数でインスタントン数を表す。$U(1)_A$ は完全に破れるわけではなく離散的な部分群は残る。(この点については後で議論する。)