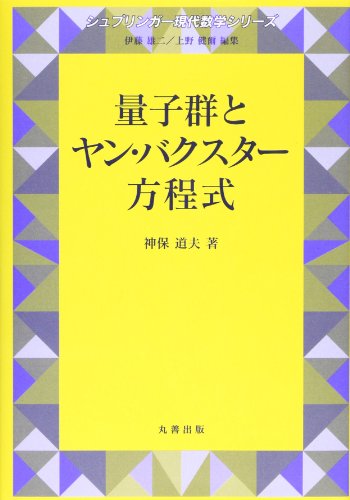9.2 アインシュタイン方程式の現代的な導出
前節では点粒子の運動方程式を計量がローレンツ不変であることから導出できることを見た。今節では計量の運動方程式、すなわちアインシュタイン方程式を対称性に基づいて考える。以前触れたように、計量は物質の分布から動力学的に決定できる。アインシュタイン方程式を求めるにあたり、まず望まれる全ての対称性のもとで不変な作用を書き出すことから始めよう。リーマン多様体上でそのような作用は
\[ \S \, = \, - \int d^4 x \sqrt{- \det g} ~ \Bigl( \mbox{不変な項} \Bigr) \tag{9.13}\]
と表せる。ここで、積分測度 $d^4 x \sqrt{- \det g}$ は座標変換のもとで不変である。ミンコフスキー空間上で座標変換のヤコビアンは $\sqrt{- \det g}$ の因子によって相殺される。ここでは詳細は省略するが、例えば、平坦な計量 $ds^2 = dt^2 - dx^2 - dy^2 -dz^2 = g_{\mu\nu} d x^\mu d x^\nu$ から球面の計量 $ds^2 = dt^2 -dr^2 - r^2 d\th^2 - r^2 \sin \th^2 d \varphi^2 = \tilde{g}_{\mu\nu} d \tilde{x}^\mu d \tilde{x}^\nu$ への座標変換を考えると、積分測度は $ d^4 x \sqrt{- \det g} = dt d x dy dz \rightarrow r^2 \sin \th \, dt dr d \th d \varphi = d^4 \tilde{x} \sqrt{- \det \tilde{g}}$ と変換するので、$\int d^4 x \sqrt{- \det g}$ が不変量であることはすぐに確認できる。
定数を除くと、(9.13)の不変な項はリーマン曲率テンソル ${\cal R}^{\la}_{\mu \nu \al} $ で表せると予測できる。これは8.3節で計算したように ${\cal R}^{\la}_{\mu \nu \al} $ がローレンツ共変であることから分かる。(8.44)で定義したようにリーマン曲率テンソルは
\[ {\cal R}^{\la}_{\mu \nu \al} \, = \, \d_{\mu} \Ga^{\la}_{\nu \al} - \d_{\nu} \Ga^{\la}_{\mu \al} + \Ga^{\la}_{\mu \bt}\Ga^{\bt}_{\nu \al} - \Ga^{\la}_{\nu \bt}\Ga^{\bt}_{\mu \al} \tag{9.14}\]
で定義される。ただし、クリストッフェル記号 $\Ga^{\la}_{\al\bt}$ は
\[ \Ga^{\la}_{\al\bt} \, = \, \frac{1}{2} g^{\la\mu} \left( \d_\al g_{\mu \bt} + \d_\bt g_{\mu \al} - \d_\mu g_{\al\bt} \right) \tag{9.15}\]
で与えられる。${\cal R}^{\la}_{\mu \nu \al}$ から不変量を求めるには、添え字の縮約を考えるのが便利である。つまり、${\cal R}^{\la}_{\mu \nu \al} \rightarrow {\cal R}^{\la}_{\la \nu \al} \equiv {\cal R}_{\nu \al}$ とおく。具体的に、${\cal R}_{\nu \al}$ は
\[ {\cal R}_{\nu \al} = \d_{\la} \Ga^{\la}_{\nu \al} - \d_{\nu} \Ga^{\la}_{\la \al} + \Ga^{\la}_{\la \bt}\Ga^{\bt}_{\nu \al} - \Ga^{\la}_{\nu \bt}\Ga^{\bt}_{\la \al} \tag{9.16} \]
と表せる。${\cal R}_{\nu \al}$ はリッチ・テンソルと呼ばれる。$\Ga^{\la}_{\nu \al}$ は$\nu$, $\al$について対称であったので、$\d_\nu \Ga^{\la}_{\la \al}$ が$\nu$, $\al$について対称であれば、${\cal R}_{\nu \al}$ も$\nu$, $\al$について対称であることがすぐに分かる。この対称性は次のように確認できる。(9.15)から $\Ga_{\la \al}^{\la} = \hf g^{\la \mu} ( \d_\al g_{\mu \la} )$ である。よって、$\d_\nu \Ga^{\la}_{\la \al} = (\d_\nu g^{\la\mu} )( \d_\al g_{\mu\la} ) + g^{\la \mu} (\d_\nu \d_\la g_{\mu \la}) = - \Tr ( \d_\nu g \, g^{-1} \d_\al g \, g^{-1}) + g^{\la \mu} (\d_\nu \d_\la g_{\mu \la})$ と計算でき、これは $\d_\nu \Ga^{\la}_{\la \al}$ が $\nu$, $\al$ について対称であることを明示している。
ここで、計量テンソル $g_{\mu \nu}$ も添え字について対称なので、非自明なスカラー量
\[ {\cal R} \, = \, g^{\nu \al} {\cal R}_{\nu \al} \tag{9.17}\]
を求めることができる。これはリッチ・スカラーあるいはスカラー曲率と呼ばれる。半径 $r$ の球面のスカラー曲率は $r^{-2}$ に比例することが知られている。
対称性の原理から、不変な作用(9.13)は形式的に
\[\begin{eqnarray} \S &=& - \int d^4 x \sqrt{- \det g } ~ \Bigl[ \mbox{(定数)} + c \, {\cal R} + \bigl( {\cal R}^2 , \, {\cal R}_{\nu\al}{\cal R}^{\nu\al} , \, {\cal R}^{\la}_{\mu\nu\al}{\cal R}^{\mu\nu\al}_{\la}, \, \cdots \bigr)\Bigr] \nonumber \\ &=& - \int d^4 x \sqrt{- \det g } \left[ \frac{1}{16\pi G} {\cal R} + \La \right] \, + \, \cdots \tag{9.18} \end{eqnarray}\]
と書ける。ただし、$c$ は比例係数である。ここでは、後の便宜上 $c$ を $\frac{1}{16\pi G}$ と固定した。$G$ はニュートンの重力定数である。$\La$ は宇宙定数と呼ばれる定数を表す。$G$は非相対論的な極限を考えると同定できる。この点については次回に後述する。上式2行目ではスカラー曲率 ${\cal R}$、リッチ・テンソル ${\cal R}_{\nu\al}$、リーマン曲率テンソル ${\cal R}^{\la}_{\mu\nu\al}$ に関する2次以上の項を省略した。
つぎに、作用(9.18)の変分を考える。スカラー曲率 ${\cal R} = {\cal R}_{\al\bt} g^{\al\bt}$ の変分は
\[ \del {\cal R} \, = \, \del {\cal R}_{\al\bt}\, g^{\al\bt} \, + \, {\cal R}_{\al\bt} \del g^{\al\bt} \tag{9.19} \]
で与えられる。また、$\sqrt{- \det g }$ の変分は次のように求まる。$M$ を可逆な行列とすると、恒等式
\[ \log \det M \, = \, \Tr \log M \tag{9.20} \]
から、関係式
\[ \del ( \log \det M ) \, = \, \frac{\del ( \det M ) }{ \det M } \, = \, \Tr M^{-1} \del M \, = \, - \Tr M \del M^{-1} \tag{9.21} \]
が分かる。よって、$\sqrt{- \det g }$ の変分は
\[ \del \sqrt{- \det g } \, = \, - \frac{1}{2} \sqrt{- \det g } \, g_{\al\bt} \del g^{\al \bt} \tag{9.22} \]
と計算できる。よって、曲率の2次以上の項を無視すると(9.18), (9.19), (9.22)から
\[\begin{eqnarray} \del \S &=& - \int d^4 x \sqrt{- \det g} \left[ - \frac{1}{2} g_{\al\bt} \left( \frac{1}{16 \pi G} {\cal R} + \La \right) + \frac{1}{16 \pi G} {\cal R}_{\al\bt} \right] \del g^{\al\bt} \nonumber \\ && - \int d^4 x \sqrt{- \det g} \, \frac{1}{16 \pi G} \del {\cal R}_{\al\bt} g^{\al \bt} \tag{9.23} \end{eqnarray}\]
と求まる。